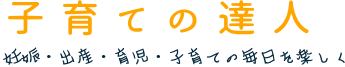塾に付いて回る悪のイメージはどこから来たのか
日本において「塾」という民間の教育機関は、江戸時代の寺子屋の頃から、各時代の親や子供のニーズに応え、柔軟に変化してきました。しかし、現代においても塾に対してネガティブなイメージを抱く人がいます。塾はなぜ悪のイメージを抱かれるのでしょうか。教育の歴史と塾の歴史を関連付けながら、塾が本当に悪であるのかを今一度考えていきましょう。
「乱塾」とはなんだったのか
「塾」と聞いて、ある程度以上の年齢の人がイメージするのは、小学生が「必勝」の鉢巻を巻き「絶対合格!」の声を上げる様子や、眼鏡をかけた秀才が感情を忘れたかのようにひたすら問題集に取り組む様子、もしくは子の成長への投資として高額な授業料を取る金儲け目的の教育機関、とまで言うと極端ですが、とにかくネガティブなイメージが湧く事は多いでしょう。
毎日新聞の社会部が1977年に刊行した『乱塾時代』という本では、当時の異常なほどの学習塾ブームについて「心身ともに未発達である小学生に、学校に加えて塾に通わせて長時間の勉強を強いる事が、彼らの将来にどのような影響を与えるのか予測が難しい」という旨の苦言を呈しています。
「友達や家族とのコミュニケーションの時間が減り、塾での点取り競争に熱中した結果、他人を顧みない大人になるのでは」とまで述べています。
1977年というと中学受験が注目を集め始めていた頃です。その注目は中学受験熱への批判で、新聞の紙面は「乱塾」という言葉で賑わい、塾、ひいては子供を塾へ通わせる親へのバッシングが盛んになっていました。
ですが、塾そのものが悪いものではないという事は、当時の記者も分かっていた事でしょう。塾が子供たちを拉致監禁し、勉強を強制しているのならともかく、もちろんそういう訳ではありません。ただ社会の中で塾への期待が高まりすぎた結果、そういう状態になってしまったのです。
その頃、高度成長期にあった日本では、第1次産業から第2次、さらに第3次産業へと人が流れていました。地方から都市部へと人が流出し、知的労働階級が作り出されていきました。
同時に「教育投資論」「人材開発」「マンパワーポリシー」といった、子供たちを労働力、人材に効率の良いものとして育成していこうという産業界と国の思惑が強まり、そうした中で知的労働者として良い地位を獲得すべく、学歴信仰も加速していきました。
一部の都立進学校に志願者が集中する事を避けるべく、東京都は1967年に、都立の高校を幾つかずつの群として分け、受験者の希望に関わらず進学校を振り分けてしまう「学校群制度」という強引な制度を導入します。
それまで東大合格者数で首位にあった日比谷高校が実績を下げ、1970年代のうちに、他の都立名門高校も含め、あっという間に私立中高一貫校に進学実績において追い抜かれ、引き離されてしまいました。
エリートの王道とでも言うべき日比谷高校などが年々合格者数を減らし、灘だ開成だと毎年その首位が入れ替わる東大合格者数は、乱世の下克上の如くとして話題性が高く、毎年春には週刊誌が東大合格者特集を組んでいました。
そういう勢いに乗って中学受験進学塾も勢いを増して、それを新聞各紙が「乱塾」とうたい、紙面を賑わせたのです。
日本の教育において1968年は象徴的な年でした。この年に告示された過密な学習指導要領は「新幹線授業」などと呼ばれるほどのもので、授業についていける子供は小学校で7割、中学校で5割、高校ともなると3割程度という状況になりました。
この事を「七五三教育」という言葉で揶揄し、同時に「落ちこぼれ」「詰め込み教育」という言葉も使われ始めました。そういう新聞記者のネーミングセンスが、教育に過ぎた期待を寄せる世間の人々の気持ちを揺さぶりました。
この頃の「詰め込み教育」を省みて、後に「ゆとり教育」が考案されました。この「ゆとり教育」の導入後、またも塾が存在感を増し、中学受験塾が活性化したのは記憶に新しい事です。教育の変革期において、塾は必ずなんらかの役割を果たすのです。
「乱塾時代」というのも、塾が乱立するような結果となってしまった世の中の状態を揶揄したものです。日本の教育が競争主義的になってしまった事に対し、警鐘を鳴らしていたのです。
「塾での点取り競争に熱中した結果、他人を顧みない大人になるのでは」という危惧も、的外れだったとは言いがたいですが、悪いのは塾ではなく、そこまでして子供を教育しなくてはならない世の中の状態でした。
しかし、塾が子供から遊びや時間を奪い、点取り競争を強要している悪の存在だと勘違いした人もいました。文部省ですら、塾を疎ましく思っていたのです。
塾を認知させたのは「ゆとり教育」だった
1980年に初めて「ゆとり」という言葉で呼ばれた学習指導要領が実施されました。「ゆとり教育」といえば、1992年の「月1回の学校週5日制導入」と2002年の「学校完全週5日制導入」や「円周率を3とする」という動きを思い出しますが、「ゆとり」の起こりは1980年の事でした。
80年代になり、第2次ベビーブーム世代が就学し、1986年以降はバブル景気も手伝って、中学受験はさらに熱を増しました。「詰め込み教育」は終わりましたが、乱塾時代は終わらなかったのです。
21世紀になると、塾業界は少子化の波の到来に対して生徒数の減少を危惧しましたが、極端に進められた「ゆとり教育」が塾業界には幸いし、その追い風となりました。国全体で実施された調査などの結果を見ると、通塾率が年々増加している事がよく分かります。
文部省が1976年3月に発表した「児童・生徒の学校外学習活動に関する実態調査」によると、その頃の通塾率は小学生で12%、特に6年生に限っては26.6%、中学生では38%でした。
2010年度の文部科学省発表の「子どもの学習費調査」によると、公立小学校に通う生徒の通塾率は全国平均39.4%、公立中学校の生徒においては全国平均71.1%です。
2013年の「全国学力・学習状況調査」に付随した調査の結果によると、小学6年生の通塾率は全国平均で49.7%、東京都に限っては59.4%で、中学3年生の全国平均は60.4%です。
小学6年生ともなると、全国で見ても、ほぼ半数が塾に通っているのです。通塾は現在においてはごくごく一般的な事といえるでしょう。
教育機関としての塾の存在を、文部省も認めざるをえない状況になりました。1999年には、文部大臣の諮問機関である生涯学習審議会が学校と塾の共存について文部省に答申し、正式に共存を認めました。
これを新聞各紙も大々的に報道し、それらは文部省が塾と友好的な関係を築くべく歩み寄ったかのように世間には受け取られましたが、文部省と塾業界の間では、表立たないところで激しい攻防が繰り広げられていました。
文部省は塾の存在を教育機関として認めながらも、19時以降の授業を禁止するといった内容の「塾規制案」を用意していたのです。
文部省としては、2002年から実施される「ゆとり教育」に伴って、土曜日が自由になった小学生の通塾が増えるのではないかという懸念もあり、塾の存在を認めたうえで規制案を出す事で、塾の動きを牽制する思いもあったと推測出来ます。
当然規制案に対して塾は業界全体で反対しました。元塾経営者でもあった衆議院議員の下村博文が仲介し、塾の業界団体と文部省担当者による会合が複数回行われた結果、規制案は見送られました。
そして2002年に実施された「ゆとり教育」が、塾に対しての好意的な見方を世間に広める役割を担い、塾は教育機関としての認知を得たのです。
あらゆる「塾」は全て「進学塾」である
「塾」と聞いて、人によっては大きな駅の前に一際目立つ看板を掲げている大手の塾を思い浮かべたかもしれませんし、人によってはそれぞれの地元に密着した個人塾を思い浮かべたかもしれません。それに、中学受験者を対象にした塾もあれば、中学の定期試験で良い点数を取る事を目的とした塾もあります。
50年以上に渡り塾を経営している佐藤勇治氏は、塾を「パートタイムの勉強会」と表し、またPS・コンサルティング・システム代表の小林弘典氏は「上級学校へ進学するためのパートタイムの教育機関」と表しました。「塾はすべて、広い意味では進学塾といえる」とも述べています。
元国立教育政策研究所の結城忠氏は塾を「総合塾」「進学塾」「補修塾」「救済塾」の4つに分類しましたが、小林氏は「補習塾と考えられている塾であっても、最終的な目的は受験であり、補習塾と進学塾との違いは集まる生徒のレベルの違いでしかない」と言っています。
進学塾としても補習塾としても機能するという意味で総合塾という呼び方をしているわけですが、小林氏の考え方から見れば、単純に対象に広い学力層の生徒を取る進学塾であるという事です。
小林氏は、また救済塾という呼び方については特に、「出来ない子を救済する塾という意味だろうが、そんな上から目線ではそのような子たちの力を引き出すことは出来ない。生徒や保護者の立場からしてみても、あたかも自力ではどうにもならないような言い方をされるのは嬉しくないだろう」と苦笑します。
教育評論家の小宮山博仁氏は、救済塾を「教育理念塾」と言い換えました。これもまた、小林氏の考え方によるならば、学力の低い層に対して情熱と技術を以て勉強を教える進学塾である、といえるでしょう。
ここでは、小林氏の考え方に則り「塾、すなわち進学塾とは、上級学校へ進学する事を目的とする、パートタイムの教育機関である」と定義します。
なおこの定義からいくと「塾」と「予備校」は似て非なるものという事になります。予備校というのは、浪人生のための「フルタイムの教育機関」だからです。しかし最近は予備校でも塾と肩を並べるようなサービスが受けられるので、全くの別物という事でもありません。
塾の起源はいつだったのか
お金を払っても我が子に教育を、という思いは、日本では全国に1万も寺子屋があった江戸時代の頃からもしっかりと見る事が出来ます。その頃の日本の人口は現在の4分の1から5分の1ほどで、現在、日本には全国に5万ほど塾があります。つまり江戸時代にはすでに、現在の塾と同程度の割合で寺子屋があったという事です。
江戸時代や明治初期にも私塾は数多く存在しました。吉田松陰の松下村塾や、福沢諭吉の蘭学塾(慶應義塾)などがそれです。これらは現在の感覚で捉えれば、どちらかといえば塾というよりも専門学校や大学に近い性質のものでした。
また受験指導を目的とする民間の教育機関もありましたが、これらもほとんどはフルタイムの教育機関だったので、今でいうなら予備校に近いものです。
では現在のような塾はいつどこで起こったものかといえば、1912年に浅草に出来た島本時習塾であるとされています。この塾は日本で最も古い学習塾として、ギネスにも認められています。
その頃、上級学校へ進学するための指導は、大体が学校で行われていました。そんな中で浅草小学校の教員だった島本龍太郎が、旧制中学へ進学する事を希望する生徒たちを集めて休暇中に勉強合宿を行うなどして進学指導を行いました。
ところが島本は校長との対立が原因となって離職します。それを惜しんだ保護者たちから希望されて、民家で中学受験のための勉強会を開くようになったところ、下町の名門校への合格者が多く輩出された事が評判になり、生徒はどんどん増えていきました。
旧制中学への進学を希望する生徒が増えた事もあって、同じような塾が他にも出来るようになったのです。旧制中学というのは、小学校と大学の間の5年間の中等教育学校の事で、現在で言うならば中高一貫校と同じようなものですから、塾の起こりは中学受験塾であるといえるでしょう。
「乱塾キャンペーン」の中でも塾は発展した
戦後、現在の6年、3年、3年、4年制の単線型学校制度になるなど、学校制度が大きく改訂され、同時に学校で進学指導を行わなくなったため、塾は存在意義を大きくしていきました。
高校進学率は、ベビーブームや高度成長期に伴う高学歴志向により、一気に高まっていきました。中学校が義務教育化し、学歴競争の最も激化する地点は高校受験となりました。戦後も名門私立中学を目指す生徒は一定数いて、戦後から続く中学受験文化は途絶えこそしなかったものの、少数派となりました。
産業構造の変化から、特に地方から上京する若者が増加し、学歴は一層重視されるようになっていきます。出自に関わらず新しい社会を有利に渡っていくための通行手形こそが学歴となり、1950年に42.5%だった高校進学率は、1975年には9割を超えていました。
単線型学校制度になって、ほぼ全ての子供たちが同じように教育を受けるようになった事から、序列化は避けられない事態でした。みなに平等な教育の機会を、という理念を推し進めた結果、教育は大衆化され、子供により良い社会的地位を獲得させるために教育熱はどんどん高まり、皮肉にも国全体で教育競争が始まってしまったのです。
そうして全国に塾が次々開かれました。そのように戦後の塾は、塾の起こりの頃と違い、主な舞台を高校受験に発展していきました。
しかし1970年代といえば「乱塾時代」の頃です。東京都が「学校群制度」を導入した結果、東京では公立高校回避の風潮が起こり、戦後は少数派となっていた私立中学受験が再び過熱しました。
全国に高校受験を目的とする進学塾が開かれ、また東京都やその周辺県では中学受験のための進学塾の需要が高まっていきました。
中学受験の批判を目的に始められた「乱塾キャンペーン」は、中学受験塾のみならず、高校受験塾までをも巻き込んで、社会に「塾=悪」というイメージを刷り込む事に成功しましたが、塾業界は不思議にもその後も拡大を続けていきました。
大衆の中で「塾=悪」とみなされながら、それでも親は子供を塾へと通わせたのです。子供を塾へ通わせ、遊びの時間を奪って勉強に従事させる親であると批判を受けると分かっていながらも、教育をあきらめる事は出来ない、仕方ないという思いだったのでしょう。
そのように、子供により良い教育を受けさせてあげたいという親心や、学びたいという子供の気持ちがあったとしても、それを表立って主張出来ない時代になってしまっていました。早いうちから子供を塾へ通わせれば「教育ママ」などと呼ばれ、塾へ通う子供は、友達に気付かれないようにしなくてはなりませんでした。
自分が努力していても、それを周りは白い目で見るのですから、そんな状況では、やる気も自信も失い、それどころか卑屈な気持ちにすらなります。
子供は勉強それ自体ではなく、勉強に精を出す事で世間から白い目で見られる事が嫌で塾へ通う事が嫌になり、親はそれでも塾へ行って勉強するようにと子供に言わなければならないので、親子の間でも衝突が起きます。
そうして日本では、スポーツに励む子供は、子供らしくて良いと褒められるのに、勉強に励む子供は、可哀想だなどと勝手に同情されるようになってしまいました。
「乱塾キャンペーン」は、塾を減らすとか、中学受験熱を冷ますとか、本来の目的としての機能は果たさず、ただ全国の子供たちに、勉強に対する斜に構えた態度を広めるという結果をもたらしただけでした。
塾業界の市場規模はどれくらいなのか
1970年代半ば以降、塾業界は拡大期を迎えました。小林氏はこの時期、塾の創業者の持つ経歴の傾向が変化したと指摘します。
それ以前の塾創業者は学校の教員出身者がほとんどでしたが、この時期以降、大学在学中の学生や、他の業種から転職してきた人が塾を開く事が増えました。教員の待遇が以前よりも改善されて教員職を離れる人が減った事や、大学紛争によって大学を抜けた高学歴者が多く出た事、また一般企業への就職難などの原因が重なっての事でした。
これによって塾業界は教育者の集まりから起業家の集まりへと体質を変え、塾が産業として成立するようになったのだと小林氏は分析しています。
教育競争の動きが高まる中で学びの場の需要が増え、塾が増加していった様子は、現在のIT業界の様と似ているといえます。
2009年時点で株式を上場していた塾20社のうち、半数以上が1970年代に創業、法人化しており、中でも早く上場した5社は全て1970年代の創業で、かつ1976年に法人化していました。そうした塾が業界を引っ張って、塾業界は一大産業へと発展していったのです。
塾業界の市場規模は、1970年代半ばから1993年にかけて、急激に拡大しました。全国の塾の数は、1990年代には約5万にまで増加しています。しかし、1994年を境に、少子化とバブル崩壊後に長く続いた不景気のあおりを受け、市場規模は横ばいとなりました。
小林氏の計算によると、2011年の塾業界の市場規模はおよそ1兆3240億円にのぼり、また矢野経済研究所は2012年の市場規模を前年比1.5%増の9380億円としています。算出の基準が異なっているために2つの数字に違いが見られますが、およそ1兆円規模の市場と見て間違いはありません。
塾を繁栄させた土壌は江戸時代から続く教育意識
塾業界の規模が1兆円という事は、日本全国の子供を持つ保護者たちが、子供の教育のために、学校以外にも1兆円もの金額を支払っているという事です。
日本における子供1人あたりの教育支出は、世界と比較しても高い水準にあります。教育機関に対しての公的支出の国内総生産比で見ると、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中では最も低いのですが、これは大学レベルの高等教育に対しての支出が、主に私的な負担に頼っているからです。
つまり、小学校から高校レベルの教育に関してはほぼ公的財源でまかなわれており、高校まではそれらによって十分な教育が受けられる制度が整っているのにも関わらず、親は決して少なくない金額を支払って子供を塾に通わせ、大学に入ってからは学費を自分たちで負担するという環境なのです。「子育てにはお金がかかる」というのも、頷ける状況です。
江戸時代、世界的に見てもトップレベルであった日本の教育は、国家的な学校制度などではなく、地域に作られた寺子屋や、藩がエリートの育成を目指して作った藩校、また志を同じくする若者が集う私塾によって成り立っていました。
農民はなけなしの米や農作物を授業料として渡しまでして子供を寺子屋に通わせ、藩は予断を許さない財源の中でなんとか藩校を維持し、私塾のほとんどは創設者が私財をなげうって作られました。
そのように、日本では教育というのはお金がかかるのだという意識がもはや常識として根付いており、また日本人には、制度などによって与えられた教育だけでは満足出来ないという国民性があるのかもしれません。
また、戊辰戦争頃の長岡藩での教育にまつわる「米百俵の逸話」も日本の教育の見方として象徴的です。北越戦争において敗れ、財政が乏しくなって食べるものにも困っていた長岡藩に、支藩から百俵の米が贈られた際、藩の長官に次ぐ官職にあった小林虎三郎は米を売却し、それを費用として学校を設立したという内容の逸話です。
このように日本には、目先の贅沢よりも将来的な効果を鑑みて教育を重要視する文化も強く根付いています。
明治以降、近代的な学校制度が整えられていく中で、寺子屋が母体となって小学校が作られたり、藩校が旧制中学になるなどした例も多くあります。親が子供に労働させる事から子供を守るために整備されたという西洋の学校制度とは、日本のそれは成り立ちからしてずいぶん違っているのです。
そうした教育に対して熱心な国民性や文化が、全国に5万もの塾が開かれる基盤となったのでしょう。
公教育と塾との連携が日本の教育を発展させた
明治になると、読み書きやそろばんを教える事を中心とした小学校とエリートの養成を目的とした大学との中間教育として旧制中学が出来るなど、国が学校制度を整備しました。
するとその受験対策として塾が生まれ、さらに学校教育が上級学校への進学指導を手放した戦後にも、上級学校が試験による入学者選考を続けたため、その対策として塾が必要とされました。
高度成長期を迎え、知的労働者階級が作り出されると、国民により広く教育の手が届くようになり、単線的学校制度の中での競争が激しくなって、塾はよりいっそう必要とされるようになります。
また「学校群制度」など公立高校回避の動きが生まれ、私学受験熱が再熱した時や、「ゆとり教育」が極端に推し進められた時にも、塾はその存在感を増しました。
学校制度などに変化があると、そこに歪みが生じ、その歪みに対して、子供の親などに不安、不満が生じます。そうした不安や不満を、塾が解消してきたのです。
しかし言ってみれば、子供により良い教育を受けさせたいという国民性と、それを叶える塾という民間の教育機関があったからこそ、日本の教育制度は取り返しのつかない失敗を回避する事が出来たのです。
もしも極端なゆとり教育が推し進められた時に塾という学校外の教育機関が無ければ、日本の教育は混乱し、今ほどの学力レベルは保てていなかったかもしれません。このように塾の存在は、公教育を支え続けてきました。
そしてまた塾の役割が、親たちの持つ不安や不満を受け止めて解消する事であるという事は、親の気持ち、つまりニーズに上手く対応した塾が栄えて生き残るという事ですから、塾は、親たちの不安や不満を映し出す鏡のようなものなのです。
国の教育のうち、公教育や学校制度が大枠を担い、それぞれの時代の教育の手の届かないところを、小回りの利く民間教育の塾が担うという、意図せずして生まれた連携によって、日本の教育は進化してきたといえます。
現代の塾の役割は勉強を教える事だけではない
塾が上級学校へ進学する事を目的とする教育機関だとしても、受験のための勉強を教えるというそれだけに役割を限定してはいけません。受験で合格すればそれで良い、という方針の塾は少なく、生徒との信頼関係を重要視し、彼らの将来を気にかける塾経営者や塾講師は珍しくなく、時にその思いは学校の教員以上のものです。
2013年6月、全国学習塾協会が公益社団法人に移行した際に、下村文部科学大臣は記念式典において、「立派な塾や私学は勉強だけでなく、マナーなども教えている事は業界内では当然の事だが、一般には塾でそういう事も教えていると思っている人は少なく、勉強を通じて道徳教育もきちんと行っている事をアピールしてほしい」という旨の発言をしました。
2013年9月の国際教育学会第8回シンポジウムにおいて、学校と塾の連携に取り組む、大阪府八尾市の須原英数教室塾長の須原秀和氏は「第4の教育カテゴリーとしての塾教育」という概念を提案しました。
かつては家庭、学校、社会と、それぞれで行われる教育が重なって機能していましたが、核家族化、女性の社会進出などの社会現象によって、3つの教育の連携が希薄になった事を須原氏は指摘したうえで、その3つを結び付ける4つ目の教育カテゴリーとしての役割を塾が担うべきであり、それが塾の社会的責任であると訴えたものです。
社会教育は地域でのつながりの希薄化によって事実上消え去り、その役割を、塾や習い事が肩代わりするようになったとも言えるでしょう。塾に通って良かった事に、塾で他校の生徒と友達になれた事を挙げる生徒も多くいます。塾は学校以外の子供の居場所にもなりえるのです。
教育評論家の小宮山博仁氏は、塾が現代教育のみならず、子供が暮らす社会までも支えている事を示しています。地域社会の教育力の欠けた部分を習い事などが補い、学校の教育力の欠けた部分を進学塾が補い、家庭の教育力の欠けた部分を塾などが補っているという事です。
このように日本にとって欠かせない社会の一部となっている塾は、日本の文化といっても過言ではないでしょう。
塾がニーズに応える事で受験競争が激化する
ここまで述べてきたように、塾の存在意義自体は誰もが認めているところです。しかし塾にはいつまでもネガティブなイメージが付いて回り「必要悪」とまで言われるのはなぜでしょうか。
大きな要因として、「乱塾時代」の影響が消え去っていない事が挙げられます。また義務教育が広く行き渡り、教育は無料であるという錯覚とも言える意識が広まった事も要因の1つです。教育は無料で受けられるはずという考えが先行し、塾業界に対し、教育とお金を結び付けるものというイメージを持つ人も少なくありません。
乱塾時代におけるネガティブキャンペーンの影響や、教育は無料であるという意識から生まれる塾へのマイナスイメージは風評といえますが、さらに、塾という教育機関が持つジレンマにも着目すべきです。
進学塾も補習塾も、すべての塾の目指すところは上級学校への進学、つまり入学試験に合格する事です。しかしその入学試験には、定員があります。
英検や漢検などの検定試験ならば、個人それぞれの能力が合格基準を満たせば、人数に関係なく合格する事が出来ます。ですが入試となると、どれだけ能力が高くともその能力を超える人が定員数以上いると、合格する事は出来ません。入試では、他の入学志願者に勝る事が必要です。
塾はその競争に手を貸します。塾で勉強し、力を付ければ受験という競争において有利になります。ですが当然、他の志願者も塾へ通って勉強します。相手が力を付けるならば、自分もそれ以上に力を付ける事でしか、受験では勝てません。オークションの競り合いのように、キリのない争いになってきます。
そして知らずのうちに競争はハイレベルなものになってしまい、競争原理により全体の学力レベルは向上しますが、子供たちへの負担も比例して増加していきます。
子供たちの進学を支えるはずの塾の存在が競争を激化させ、進学を困難にしてしまうという、この構造的なジレンマこそが、「乱塾」と声を上げた新聞各紙の糾弾したかった点なのでしょう。しかし塾は親や生徒の不安や不満、ニーズに応えているだけなのです。
受験戦争をあおるものの正体は「平等主義」
受験競争を激化させる最大の要因は、塾の構造ではなく、日本の学校制度が単線型であり、また入学の際には競争型の試験を乗り越えなくてはいけない事にあります。
日本における学校制度の目指すところは、それぞれの学校が個性的である事よりも、画一的である事で、学習指導要領や検定教科書によって、全国どこでも同じ教育が受けられる事を目指しています。遅れていく事も、あまり先を行きすぎる事も許されません。
そのため、学校はすべて偏差値によって序列化されています。偏差値のたったの1の違いでも、その1の分だけ高い数値である学校が上だとされます。すると出来る限り偏差値の高い学校に合格したいという気持ちになり、それこそが目的であると思えてきます。受験は数値が1でも高い偏差値の学校に受かる事が目的の、ゲームのようなものになっています。
教育評論家の小宮山博仁氏は、この問題について、次のように述べています。
「受験のゲーム化は、高校や大学が偏差値で細かく輪切りにされているから起きる現象である。これも受験戦争を激化させる要因の一つといえるだろう。このような受験競争意識の激化は、塾を成り立たせる加速条件といえる」
受験競争意識とは塾がもたらしたものではなく、実際はその逆で、受験競争意識が塾を成り立たせている、という指摘です。
誰もがみな、しかも全国どこにいても、同じレベルの教育を受ける事が出来て、さらに努力すればより良い学校に進学する事が出来るという日本の教育の仕組みは、世界でも稀な開かれた学校制度です。
その点は素晴らしい事ですが、出自に関係なく努力によって勝れば人の上に立つ事が出来るという仕組みは、不幸にも「学歴エリート」や「受験競争意識」を生み出してしまいました。
欧米ではなお伝統的な階層文化が根強く残っており、出自によって学歴があらかじめ決まる場合が多く、社会的な階層が固定されていて、教育は社会の平等化に対してほぼ無力である事を広く人々も認識しています。よって、過酷な競争は起こりません。
ところが日本では皮肉な事に、平等に重きをおいた学校制度によって、過酷な受験競争が起こっています。
社会学者の刈谷剛彦氏は、この事が学歴社会の基盤になっていると示唆し、「戦後の日本における能力主義と平等主義の奇妙な結合」と表現しています。
つまり塾でも偏差値でもなく、刈谷氏の言う「戦後の日本における能力主義と平等主義の奇妙な結合」こそが子供たちを受験戦争へと追い立てているのであり、塾を悪であるとする見方は一部分だけを見た狭い見方です。広く教育機関や学校制度の構造を見れば、塾が悪であるという考えは間違いであると気付く事が出来ます。
更新日:2019/11/29|公開日:2017/10/24|タグ:塾