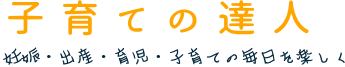子どもの頭脳を伸ばすには
およそ子どもを持つ親であれば、自分の子どもが頭のいい子に育って欲しいと願っているものかと思います。ここでは、どのようにすれば子どもの頭をよくし伸ばすことができるのかについて掘り下げてみたいと思います。
生きた体験を通して子どもを伸ばそう
そもそも、「頭のいい子」というのはどういった子どものことなのでしょうか。少し前までは、脳の重量が多いほど頭がいいと言われたことがありました。また、大脳のしわの数が多いほど頭がいいとされたこともあります。しかし最近では、脳の内部にある神経どうしが作り上げるネットワークがたくさん構築されているほど頭がいい、というのが定説になってきています。神経どうしのネットワークを密に構築するためには、数多くの経験を積むことが必要であるとされます。何かを経験したことによって得られたなごりがネットワークの形成を促していくとされているのです。
梅干しを見るとまだそれを口にしていないのにつばがわいてくるという経験は多くの人がしたことがあるかと思いますが、こうしたことが起きるのも、以前梅干しを口にしたときに酸っぱさを感じ、それによってつばが出たという経験をしたことがあるためです。酸っぱいものを口にしたときにはつばが出てくるということを知っているために起きる現象なのです。
人間は、生きていく上で必要となる知識を何らかのことを経験することを通じて蓄積していきます。そして、こうした経験は大きく分けて2つの種類に分けることができます。一つは「直接体験」と呼ばれ、もう一つは「間接体験」と呼ばれるものです。
先ほどの梅干しの例で言えば、実際に梅干しを食べてみて酸っぱさを感じる、というのが「直接体験」です。自分で実際に経験して得た知識ということで、「体験的知識」と言うこともできます。こういったたぐいの知識は、遊んだりお手伝いをしたりといったように実際に身体を動かすような体験によって得ることができます。
もう一つの「間接体験」は、実際に経験せずに得た知識であり、「法則的知識」と言うことができます。例えば読書やTV視聴を通じて得たようなものがこれに含まれます。いわゆる「勉強」で身につける知識もこちらに含まれるでしょう。外国人など今まで一度も梅干しを食べたことがない人に対し、梅干しを見せながら、「これはすごく酸っぱい食べ物で、食べるとつばが出るんです」と教えるようなものです。こういうケースでは、何度教えたとしてもつばが出てくることはありません。
梅干しの例に見られるように、体験的知識と法則的知識の間には大きな差があります。別の言葉で言い換えるなら、体験的知識は「体験」にあたり、法則的知識は「理屈」にあたるからです。同じ「梅干しは酸っぱい」という知識であっても、体験的知識と法則的知識は別物だということが、つばが出てくるか出てこないかということで分かるかと思います。
別の例で言えば、泳ぎをマスターしようという時に、プールなどに実際に行って水に入り、実際に水をかいたり水を飲んでむせかえったりしながら覚えるのが直接体験で、それによって得られる知識が体験的知識です。実際には水に入らず、「水泳のやり方は、水に入ったら手を伸ばし、水面に浮いた状態で足を交互にばたつかせて……」などという形で他人から教えてもらうのが間接体験で、そこから得られるのが法則的知識です。この場合、間接体験でいくら泳ぎに関する知識を得ても実際に泳げるようにはなりませんが、泳ぎに関する理屈は勉強していなくとも実際に水に入ってたいへんな思いをしたほうが遙かに早く泳げるようになります。
このように、体験的知識と法則的知識は知識としてはまったく違うものです。このため、どちらか片方だけでその両方をフォローすることはできません。理想を言えば、これら2つの知識が釣り合いが取れているのが望ましいと言えます。人間が使える時間には限りがありますので、すべての知識を直接体験で吸収することは不可能です。このため、そうできない部分を間接体験で会得しようとするのです。
特に子どもの時期は遊びやお手伝いを通して直接経験をたくさん積むことができるはずの時期なのですが、最近の子どもは周辺環境や勉強を優先するような親の考え方などにより、あまり身体を動かすような遊びをしなくなってきている傾向があります。また、過保護に育てられる子どもも多くなってきており、家事のお手伝いもほとんどしたことのない子どもが増えてきています。直接経験を積むチャンスを奪われた子どもが増えてきているのです。
たくさんの直接経験を積み、そこからさまざまな知識を吸収すべき子どもの時期にそうすることができなかったことにより、最近の子どもたちがさまざまな問題を抱えるようになってきているのではないかと指摘する専門家もいます。そういった点から見ても、子どものうちはより多くの直接的体験をするチャンスを与え、言わば「身体で覚える」知識を身につけさせてあげたいところです。
子どもの脳の発達を促す遊びとは
大人にとっては「遊び」というのはどちらかと言えば重要ではないものという位置づけかと思いますが、子どもにとっては違います。子どもにとって「遊び」は生活そのものであり、大人にとっての仕事や学生にとっての勉強と同じです。子どもは「遊び」を通して成長し、そこから大事なことを学んでいくものなのです。
例えば、あたりを走り回ったり公園の遊具によじ登ったりすることによって子どもは身体の筋肉をつけることができます。また、ボール投げや自転車乗りは平衡感覚を養うために重要な意味を持ちます。折り紙をしたり、ハサミで紙を切ったり、色鉛筆で塗り絵をしたりすることは指先を器用にするために非常に重要です。このように、一見なんでもない活動に見えるものだとしても、子どものする遊びは発達のためには非常に重要な意味を持っており、およそ無意味なものなどないと言っても過言ではないものなのです。
子どもは遊びを通じて知的な発達を遂げます。走り回ったり遊具を使ったりして自分の身体を動かして遊ぶことにより脳の発達が促されます。また、遊びの中で得るさまざまな直接体験により、子どもは自分とその周囲のものごとについての知識を得ていきます。その時には子どもはさまざまなものを見て、聞いて、身体で触れてみて、においをかぎ、時にはなめてみたりするなど五感をすべて使って自分の周囲を探っているのです。
また、子どもの遊びは自発的行動です。親など他人に言われて無理矢理やらされるものとは違います。あくまで自発的に積極性を持ってやるものであり、それによって楽しんでいるという点が、遊びが子どもにとって大事になるもう一つの理由になります。
子どもの脳を発達させるためには、子どもがよくやるじゃれつきが非常に重要です。こうしたじゃれつきには目立ったルールもなく、子どもはあたりを走り回ったり、親兄弟などに抱きつき、ぶら下がり、引っ張ったりぶつかったり転がったりして楽しみます。動物の子どもたちにも見られるこうした行動は、大脳を発達させるために大きな役割を果たすとされています。
このため、子どもが幼いころには思う存分じゃれつかせ、スキンシップをはかってあげるようにして下さい。そのようにすることで、小学校にあがってから授業の間じゅうきちんと勉強していられるような落ち着きを身につけることもできるからです。
子どもの考える力や決断力を育むために
自分自身で考えることができ、決断することができるように子どもを育てたい時には、毎日の生活におけるささいなことを自分でするようにしつけることが大事です。そうしてさえいれば、特段のことをしなくても子どもの考える力や決断力というものは十分に育ちます。
「ささいなこと」というのはどんなことでも構いません。例えば、子どもがまだ小さいうちは、毎日のご飯の時に献立リクエストをしてもらうというのはどうでしょうか。最初のうちは自分の好物しか言わないかもしれませんが、子どもがリクエストしたらそれを作ってあげるようにします。だんだんとやり方に慣れてきたら、自分の好物だけでなく、他の家族の好物であったり、前の日とは違うおかずであったり、肉や魚や野菜が入っているかといったような栄養バランスなどの面についても、きちんと考えてメニュー組みをするように、子どもと一緒になって考えるようにします。この時にも、子どもが決めたことをきちんと尊重してあげることが大事です。
子どもが小学校に上がったら、例えば家族で出かける旅行の行き先や日程などについても子どもの意見を取り入れてみましょう。まだ全部一人で決めてもらうことなど無理なはずですので、子どもが中心になって、家族全員から意見をもらって決めるようにするのです。この時にも、親の意見中心にならないように注意して、子どもの意見を軸にして組み上げていくようにします。
まだ子どもはよく分かっていないことも多いので、最初のうちは実現が難しいようなプランを立ててしまうかもしれません。そういう場合でも頭ごなしに否定しないようにしましょう。プランの無理な部分を修正し、他の人のまちまちな意見をすりあわせて一本化していくプロセスが、子どもにとってはよい学びの場となります。
どういった場合にでもそうですが、子どもが何かを決めたり決断しようとしたときに言ってはならない禁句があります。それは、「生意気を言うな」であるとか、「親の言うとおりにしなさい」といったような言葉です。日本の親はとかく素直な子どもがよい子どもであるというように考えがちです。親の言いつけを守らない子どもや先生の注意に従わない子ども、あるいは自分の意見を強く主張するような子どもは、従順さが足りないと断じられてしまうことが多いのです。
しかし、そのようにして教育を行ってきた結果、現在社会で問題になっている「指示待ち人間」の大量発生が起こることになった一要因として挙げられています。自分なりの意見を述べるどころか、自分の考えさえ持つことができない人物が増加してしまったのです。そうした人は職場において上司から指示されたことはできるものの自律的に行動することができず、いろいろと問題となってきています。これは、日本全体で行われてきた「素直さ」を求める子育てや教育が作り出してしまった問題と言えるでしょう。
現在はグローバル化が進み、日本国内だけではなく世界を相手にしていかなければならない時代になってきており、おそらくこの流れは留まることなく将来はますます国際化が進むものと思われます。欧米の人々のように、自分の意見をきちんと持ち、それを他人にしっかりと示すことができるような、自立した人物でなければ社会で通用しない時代に入っていくことでしょう。
一般的な傾向として、日本人は語学が得意ではありません。他人に自分の考えを表現するというシーンではこれは大きなハンデになります。それを考えれば、せめて自分の意見をきちんと持って、はっきりと他人にそれを表明できる態度を育てなければ国際社会から落ちこぼれてしまいかねません。これは国際的なシーンのみならず、国内においてもますますはっきりしたものとなっていくことでしょう。
子どもが尋ねる質問にはきちんと相手をしよう
2歳を過ぎるころから、子どもはさまざまなことに興味を示しては「これなに?」を連発するようになります。最初のうちこそいちいち教えてあげていた周囲の大人も、これが続くと次第に嫌気がさし、うるさがったりごまかしたり追い払ったりしてしまうようになります。
しかし、これは子どもを伸ばすという観点から見るとけしてやってはいけないことです。この時期の子どもに対しては、「それはおちゃわん」「あれはくるま」などと、シンプルな答えを返すだけでも十分ですので、かならず答えを返してあげるようにしましょう。子どもは名称を教えてもらうだけでもなんとなく分かった気になり、好奇心が満たされて満足してくれるはずです。
また、3歳前後になると、子どもは今度は「なぜ?」を連発するようになってきます。「水が冷たいのはなぜ?」であるとか、「空が青いのはどうして?」といったような、なかなか答えるのが難しいようなことを、しかも決まって親が忙しく働いているような時に尋ねてきたりするのです。それに対して、「いま忙しいから後にして」などとやってしまってはいないでしょうか。
また、こういった質問を、電車に乗っている時などに大声で尋ねられたらどうでしょうか。周囲の人の目が気になって、「大声出すんじゃありません」などと頭ごなしに叱りつけてごまかしてしまったりしないでしょうか。大声を出すことはたしなめる必要があるかもしれませんが、それでも質問の答えは返してあげるべきです。これは場所や状況、質問の内容を問わず言えることです。
例えば「水が冷たいのはなぜ?」という質問をされた時、どんなふうに答えればいいのでしょうか。嘘をつくのはいけませんが、このぐらいの年齢の子どもに対しては厳密に正確な答えを返す必要はありません。その日が暑い日だった場合、「冷たいお水はおいしいからね」といったような答えでも構わないのです。「お水が冷たいと気持ちいいのよね」などと、親がどう感じるかを話してあげてもいいでしょう。
質問の答えを返すのではなく、「どうしてだと思う?」といったように逆に聞き返す人もいます。たまに聞き返す程度ならばいいのですが、毎回聞き返すようなことをしてはいけません。そんなことをすれば、子どもは親に何かを尋ねても答えがもらえないため、つまらなくなって聞くこと自体をやめてしまうからです。そうなれば、「これはなぜなんだろう?」という健全な好奇心の芽を摘むことになってしまいます。
「空が青いのはどうして?」といったような、すぐに答えを返すことができないような難しい質問をされた時には、嘘を言ったりごまかしたりするのではなく、外に出て、子どもと一緒に空を見上げてみてもいいでしょう。そして、空が青くてきれいであること、それも季節や時間帯によって微妙に色あいが変わること、といったようなことに気がつかせるようにします。
お昼には青かった空が、日の入りが近づくにつれて西から赤く染まっていき、日没後はだんだんと灰色になっていく様子。曇った日には空は重たげな灰色に覆われていること。雨の日には同じ灰色であってもよりけぶって見えるということ。春は霞がかったような青だったものが、秋にはものすごく高く澄んだ青に見えること。夏はぎらついていた空が、冬にはどことなく暖かみを持って見えることがあること。そういったような微妙な違いを子どもと一緒に探し、自然というものが美しく、不思議で、広大で素晴らしいものだということを教えてあげるようにするのです。
子どもと一緒に空を眺めていても、読み書きできるようになるわけでも計算ができるようになるわけでもないのですが、こういう経験をすることによってより大事なものを子どもは身につけることができます。それは、あらゆることに興味を向けるために必要な好奇心です。自分の周囲には不思議なもの、よく分からないことがらが溢れているのだということを知ることで、その秘密を解き明かしてみたいという科学的探究心を抱くきっかけにもなりますし、ものごとを深く考える能力の端緒ともなっていきます。自然が持っている美しさを感じ、どうしてそうなるんだろうと不思議に思うという経験は、子どもにとっては大きな宝物になるのです。
このように子どもがいろいろと尋ねてきたときに、親や家族がどれだけちゃんと対応したかによって、子どもの将来的な伸びしろが決まると言っても過言ではありません。尋ねられたときに手が離せない状態だったとしても、あるいは人の目が気になる場面であったとしても、面倒がったりごまかしたりせずにきちんと対応してあげることにより、子どもの知的好奇心が育つのだということを常に念頭に置くようにして下さい。
テストで間違った時でも叱らずに褒める
子どもが学校のテストでよくない点を取ってしまった時、「なんでこんな点数になったの!」と叱りつけてしまう親が多いのではないかと思います。気持ちとしては分からなくもありませんが、そこで少し考えてみましょう。子どもを叱りつければ次のテストでいい点が取れるものでしょうか。
実際のところ、悪い点数だったときに叱ったとしても次のテストがよくなったり、成績が伸びるということはありません。どちらかといえばそれとは反対の効果が出てしまうことのほうが多くなります。やる気をなくして、成績が落ちてしまいかねないのです。
子どもがテストであまりよくない点数を取って帰ってきた時には、叱りたくなる気持ちをぐっと抑えて、点数を取れた部分に着目してそれを褒めてあげるようにしましょう。まずはきちんとできるようになったところを見つけてあげ、それを褒めた上で、できなかった部分がどうしてできなかったのかということを子どもと一緒に探るようにするのです。
テストであまり点数が取れないという場合、必ずそこには理由があります。漢字の書き方を覚えていなかったためなのか、文章を読み解く力が足りず、問いの意味が分からなかったのか、九九があやふやなせいで計算を間違ったのか、繰り下がりがよく分かっていなかったのか、といったように、必ず間違いには理由があるのです。どんなことが理由でうまくいかなかったのかさえ分かってしまえば、あとはその部分を理解するまで練習をすることで分からなかったところもクリアすることができるようになります。
子どもが苦手な部分を教えるような場合、すらすらと問題を解けなかったり理解が遅かったような時でも絶対に叱りつけてはいけません。勉強というものは、それをする本人も我慢が必要ですが、教える方にも我慢が必要なのです。何かを学んでいるときに怒られたり叱られたりしてしまうと、教わっている方は冷静さを失い、かえって勉強が手に付かなくなってしまいます。できないことを叱りつけても逆効果にしかならないのです。
むしろ、遅々とした歩みであっても、何かできなかった部分を1つ克服できたらそれをしっかり褒めてあげるようにしましょう。褒められて嫌な気持ちになる子どもはいませんし、どういうふうに勉強すればいいのかということがわかるようになります。それまでよく分からずにいたことを克服できた、ということに喜びや自信をおぼえることもできるはずです。
子どもがテストを持って帰ってきた時に、きちんと正解できた部分を褒めず、失敗した部分ばかりあげつらって叱っていると、子どもは自信を失ってしまいます。テストで点数が取れない自分は駄目なんだと感じるようになり、叱られたときの嫌な気持ちがフィードバックして、うまくいかなかったらまた叱られる、と感じて冷静さを失い、本来解けるはずのものまで解けなくなってしまったりします。
常に悪いところばかり指摘されていいところを認めてもらえない場合、人間は何かをやろうとしたり努力しようとする意欲をなくしてしまいます。褒めることなく叱ってばかりいると、子どもの心は縮こまってしまい、自信をなくし、自尊心が傷つき、希望をなくしてしまいます。
人間というのは不完全な存在です。従って、間違うのが当たり前です。親本人も今まで数々の間違いを犯してきたはずなのに、それを棚に上げて子どもを叱りつけるのはいかがなものでしょうか。叱りたい気持ちをぐっと抑えて、誰でも間違えてしまうことはあること、何度も同じ間違いをしないように気をつけることが大事であると子どもに伝えることができれば、子どもは縮こまることなく伸び伸びと能力を伸ばしていけるようになるでしょう。
期待されて、褒められた子どもはそれだけで伸びる
自分の子どものいいところはどこか、という質問をされた時、多くの親は一瞬黙り込み、それから「うちの子どもにいいところなんてない。例えば……」といったように欠点をあげ始めます。謙遜して言っているのであればいいのですが、子どものいいところを親が見つけられていないというのであれば少々問題です。
人間は誰しも、何かしら優れたところやいいところを持っているものです。欠点ばかり目につく我が子であっても、じっくりと考えてみれば、お年寄りに優しいであるとか、友だちの間で人気者であるとか、スポーツを熱心にやっているとか、何かしらいいところが見つかるはずです。このように、親が子どもをきちんと見ている限り、必ずいいところは見つかるものです。そしてそうしたいいところに気がついた時には、子どものいいところを認めてあげ、きちんと褒めてあげることが大事です。そうすれば子どもの自信につながり、どんどん伸びていってくれるものだからです。
アメリカの心理学の研究で、ネズミの知能を調べる実験をしていた時のことです。通常、種類が同じネズミを使った場合、当然ながら同じような結果が得られるわけですが、何度か実験を繰り返すうちに、ある実験者の持ってくる結果はいつもいい結果であるのに対し、別の実験者が持ってくる結果はいつも悪い結果であるということが見えてきました。同じ種類のネズミを使っているのに、実験を担当する人が変わると違いが出ていることが分かったのです。
どうしてなのか調べてみたところ、ネズミの努力を実験者が肯定的に捉えている場合には実験でもいい結果が得られ、逆に否定的に捉えている場合にはよくない結果がでているということが分かってきました。実験を担当している人物が実験対象であるネズミをどう見ているかによって、結果が変わっているらしいことが分かったのです。
こうした結果を踏まえ、ネズミではなく人間の子どもにもこうしたことがあてはまるのではないかということで、小学生を使った実験が行われることになりました。実験は小学校の先生に協力をお願いし、子どもに一般的な知能テストを行うという形で行われたのですが、この時先生にはその知能テストが普通のテストとは違う何か大仰なテストであるかのような情報が与えられます。そして知能テストが終わった後、その結果とはまったく関係ない形で無作為に2割から3割の児童を選び、その子たちは今後伸びる可能性がある子どもだ、というような情報が先生に伝えられました。
このような条件下で、教室における子どもたちへの先生の対応をチェックしてみると、興味深いことが分かってきました。先生が授業で質問し子どもに解答させる場面で、指名する回数については伸びるとされた子どももそうではない子どもについても変わりはありませんでした。しかし、ここは重要な答えを返して欲しい、というような場面においては、伸びるとされた子どもたちを指名する回数が明らかに増えていたのです。こうなると、伸びるとされた子どもたちは大事なところで重要な答えをするチャンスがより多く回ってくることになります。
そんな場面で指名された子どもが正解を出すことができた場合、先生は確かにこの子どもは伸びるかもしれない、と考えてその子どもを褒めることになります。子どもも褒められれば嬉しいし誇らしいので、さらに頑張ろうというやる気を起こすようになります。先生がその子どもに期待することによる効果と、子ども自身が自分に期待する効果とが相乗効果を及ぼしたことになります。
伸びると言われた子どもがうまく答えを返せなかった場合、先生はその子どもが伸びると聞かされているため、自分の尋ね方に問題があったのかもしれないと考えて質問の仕方を変えてもう一度尋ねたりします。それで子どもが正解を出した場合、やはりその子はやはり伸びる子だと考えてその子どもを褒めることになります。
逆に、伸びると言われていなかったほうの子どもについては、うまく答えが返せなかった場合にはやはり駄目かと感じ、質問の仕方を変えて尋ねたりせず別の子どもを指名するということが多くなりました。先生がその子どもに期待しないことによって、子どもは自分は駄目なんだと感じるようになり、頑張ろうというやる気を出せなくなってしまうことになります。
以上の実験により、教える側が教わる側にどのように感じて接しているかが変わると、自信を得てどんどん能力を伸ばせる子どもと、自信を失って伸びなくなってしまう子どもがでてきてしまうということがわかったのです。
こういう話を聞くと、親としては学校の先生が自分の子どもに期待し、もっと褒めてくれればいいと思うかもしれません。しかし、先生はその子どもだけを見ていればいいわけではなく、多くの子どもを教えなければならない立場にあるため、そうしようとしてもできないという事情もあるかと思います。このため、子どもを褒めて伸ばすのを先生任せにするのではなく、家庭でもっと長い時間を一緒に過ごす親がその役割を担うべきなのです。毎日の生活を送る上で、どんな些細なことでも構いません。自分の子どものいいところを見つけて、それを認め、子どもを褒めて自信を与え、能力を伸ばせるきっかけを作ってあげたいものです。
更新日:2019/11/29|公開日:2015/07/08|タグ:頭脳