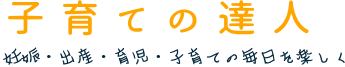教養とは、身体に刻み付けて身につけるもの
心が折れやすい日本人が、最近増えてきたように思います。それは戦前と戦後で日本の教育が大きく変わったことと無関係ではないようです。昔の寺子屋では、型を身につけるまで論語などを反復する素読が行われていました。また、禅の思想や書道など、教えを身体に刻み込ませることは日本人が得意としてきました。
身に付けた教養は「技」となり、使いこなせるようになるばかりか自分の自信にもつながり、心が強くなるのです。日本人が取り戻すべき、精神を鍛え、心を安定させる「型」の教育について考えます。
日本人にとって教養とは、身体に刻み込んでいくもの
教養とは、頭の中だけの話ではありません。ある本を読んで心から共感し、本の世界に入り込んだ後、そこからなかなか抜け出せなくなった経験はありませんか?これこそが、教養が身体に入り込んだ状態です。口調がうつってしまったり、本に登場した街に出かけたくなったりするのは、体全体でその本の世界を味わっているのです。
日本人は昔から、教養を文字通り「身につける」ことが習慣づいています。いわゆる「三道」と呼ばれる、茶道、華道、書道のお稽古では、本を読んで暗記することよりも、型を身体で覚えられるようになるまで、基本動作を反復することに重きを置いています。また、正座や箸の持ち方なども練習して身に付けて行きます。
歌舞伎や能の熱心なファンは、名場面が頭に入っており、再現することもできます。そのようにできて初めて、舞台を本当に味わい、自らの教養となったことになるのです。日本人はその文化的特性からも、教養を身体に刻み込むことは得意であるとも言えるでしょう。
声に出してこそ味わいがある文学
身体に教養を取り込んできたのは、もちろん日本人だけではありません。ヨーロッパ各国の詩は、古代から中世にかけて存在した吟遊詩人がルーツとなっており、朗読してこそその良さが分かります。当時、知的社交を楽しむ場であったサロンにおいても、詩の朗読は楽しみの一つでした。
イギリスの文豪シェイクスピアの書いた有名な詩集「ソネット」も、声に出して朗読すると、そのリズムの美しさが心に響きます。ソネットは14行からなる定型詩で、ルールに則って韻が踏まれているのですが、朗読する際の独特の抑揚とリズム感が際立つように作られています。
日本でも詩の朗読はひとつの文化として根付いてきました。ポエトリーリーディングと呼ばれ、1960年代ごろから詩人の白石かずこさんや谷川俊太郎さんが始め、現在ではライブハウスやカフェ、バーなど様々な場所で開催されています。実際に聴いてみると、詩は朗読を前提として作られていることが実感できます。
散文でも、朗読したときのリズム感を大切にしている作家は数多く、夏目漱石もその一人です。村上春樹が指揮者の小沢征爾との対談の中で、漱石の文章はとても音楽的だと評していますが、その村上春樹の文章も非常にリズミカルで、よどみなく読み進めることができると言われます。
村上春樹は、文章を書くことは音楽を演奏するのに似ていると語っています。なかでもリズムを重要視して創作活動を行っているのだそうです。
リズム感のある文体は読んでいて飽きることがなく、また、声に出して読んでみた時にもスッと頭に入ってきます。スッと入ってきたものは、身体が覚えていて、語り口ごと再現できるようになります。
『平家物語』は、元々は琵琶法師の弾き語りによって口頭伝承されてきたものです。その言葉だけでなく、節回しや琵琶の音色までが一体となった芸術であると言えます。また、日本文学の名作には、朗読してこそ文章の美しさが際立つものが数多くあります。それは日本が、古来より教養を身体に刻み込んできた伝統と無関係ではありません。
本の内容を身体に刻み込む「素読」という方法
皆さんは、時代劇などで寺子屋に集まった子供たちが、本を読んでいるシーンをご覧になったことはありますか?師範の声に続いて、子供達が声を揃えて読み上げているのは「論語」の一節です。
江戸時代の寺子屋で行われていた教育法の一つに「素読(そどく)」があります。素読とは、古典の一節を声に出して繰り返し読むことを言います。文章の意味は考えず、その文を暗唱できるようになるまで何度も音読することにより、身体に覚え込ませることが素読の目的です。
ただ文章を目で追っただけの読書とは違い、耳で聞き、声に出すことで身体に染み込ませるため、より深く理解することができ、その本が身体の一部になるのです。
したがって、教育として素読を行った世代の教養レベルは、他の世代とは比較のしようがありません。夏目漱石や森鴎外、幸田露伴などいわゆる明治の文豪、そして福沢諭吉などが「素読世代」にあたりますが、彼らの作品は、身体の中から自然に湧き出てくる教養にあふれています。
漢文や古典だけでなく、欧米の名文に至るまで、こともなげに引用することができたのは、素読で培った教養が、まさに身体に刻み込まれるレベルに達していたことを表しています。そんな教養人の作品はやはり、音読して味わってみたいものです。
この世代の作品でもう一つ特筆すべきは、文の読みやすさです。声に出して読んだ時のリズム感、身体へ染み込みやすい文体かどうかを意識して書かれており、多くの読者を引きつけました。特に夏目漱石の文体は、深い内容でありながら誰が読んでもわかりやすく、時代を超えて国民的作家として君臨しています。
深いテーマを、伝わりやすい言葉を選んで紡ぐというのは、次元の高い教養が身体に刻み込まれているからこそできる技であるとも言えます。現代でこの技を持っている作家の一人は、村上春樹でしょう。深い心理的テーマを扱いながらも読みやすく、リズム感ある文体とストーリー性を失わない点は、国民的作家と呼べるのではないでしょうか。
なお、「素読世代」の後には、芥川龍之介や菊池寛、山本有三など、大正時代の「教養世代」が続きました。この時代における教養は、身に付けていないのが恥であるとされていました。知識を取り入れるために貪欲に本を読みあさっていた世代であり、本の読み方が決定的に違っています。
日本人が失いかけている「禅の思想」
かつて寺子屋では素読が行われていましたが、主に教科書として使われていたのは『論語』です。それは、師範が門下生に『論語』の内容を教えるということとは少し違った意味を持っていました。偉大な孔子の教えを、共に学んでいるという位置づけだったのです。
寺子屋では、ただ本を読めばいいだけではありません。学ぶ姿勢も重要なポイントでした。孔子のありがたい教えを受ける場であり、門下生たちは草履の脱ぎ方、揃え方から生活態度まで整えるよう指導されていました。皆が揃って姿勢を正し、学んだからこそ教養が身体の隅々まで染み渡ったのでしょう。
同じように日本人の精神的支柱となった教えがあります。それは「禅」の思想です。スティーブ・ジョブズが傾倒したこともあり、外国の方たちから非常に注目されていますが、禅を理解し、説明できる人が日本にいったいどれだけいるでしょうか?
素読文化の衰退により論語を知らない日本人が増えたように、禅を体得している日本人も少なくなっています。
禅の考え方では、心がけ次第で、どんな場所でも修行の場とすることができます。座禅をするときだけではなく、朝目覚めてから夜眠るまでの、仕事や生活すべてにおいて、どれだけ集中することができるかが重要で、日々それらを実践すること、その積み重ねが悟りの道へと繋がっているのです。
余計なものを削ぎ落とし、自分の内面と対話するために座禅をするという、禅の思想を本当に理解するのはたやすいことではありませんが、日本人として生まれたからにはその骨格だけでも理解しておく必要があるでしょう。
『論語』にしても「禅」にしても、かつての日本人の精神的支柱であったものが何故失われかけているのでしょうか?理由として、第二次世界大戦での敗戦により、戦前・戦中までの思想や教育が、軍国主義的なものとして一旦断ち切られてしまったことが挙げられます。日本人の教養のためにも、今こそこれら精神的な柱を取り戻したいものです。
身体に「型」を刻み込み、精神を鍛えると心は強くなる
教養は頭の中だけに詰め込むものではなく、身体に刻み込ませてこそ力を発揮します。例えば歌舞伎を観る時も、セリフの声色、役者の身体の動き、衣装などをトータルに味わうからこそ、教養として身体に染み込んでいきますし、茶道のように型を繰り返し稽古することが習得の道とされる教養もあります。
また、教養はただ身に付けて終わりではなく、知りえた事実に素直に感動し、「すごい!」と驚くことができる感性も併せ持つことが求められています。特にこれからの時代に、教養を生かして社会で活躍していくためには欠かせない要素です。
人の心は本来弱いものであり、精神的な支えとなる何かが必要です。教養こそ、太い柱となって心を支えてくれるものです。教養を通じてこれらの武器を手に入れることによって、自分の内面はより強くなり、折れない心を持つことができるようになります。心と精神的な支えとなる教養、そして身に付けた「型」や「習慣」、この3つのバランスが重要です。
精神の支えとなるものの代表格には、宗教があります。聖書などの教典は、人生そのものの支えになるほど完成度の高い叡智の宝庫です。「型」「習慣」としては、念仏をとなえることや座禅を組むことが挙げられます。これらは、繰り返し身体に習慣として刻み込むことで、心の平安を手に入れることができます。
もっと身近なところでは、スポーツや武道の練習も同じです。毎日の練習は、基本動作の反復や基礎トレーニングが中心ですが、これらを日々積み重ねて行くことにより精神も鍛錬され、心が整っていきます。精神、型が心を下支えするという理想型がここにもあります。
今こそ伝えたい精神と「型」の文化
スティーブ・ジョブズの愛読書として紹介された『弓と禅』は、今から70年近く前にドイツ人哲学者のオイゲン・ヘリゲルによって書かれた本で、現在に至るまで欧米を中心に読まれ続けています。
東洋哲学に興味を持ったヘリゲルは日本で研究を行っていました。やがて彼は、東洋哲学は理論ではなく、禅や修行を重ねて得られる内的な気づきによって、物事の真髄に辿り着くことを発見します。
そして自ら、「弓の神」と呼ばれた弓道家に師事することになりますが、的を射る理論ではなく、型を身につけるための反復練習ばかりの日々に不満が爆発します。
弓道をやめる決心を告げたヘリゲルを、師匠は真夜中の道場に連れ出します。そこで、目をほとんどつむったまま、2本の矢を連続して命中させる神業を見せつけたのです。この後ヘリゲルは人が変わったように修行に励み、ある日師匠からも認められたというストーリーです。
師匠が説いていた「自分ではなく、自分の中にいる『それ』が弓を放ち、的を射る」という教えを、身体をもって理解した瞬間について書かれているこの本の内容は、昔の日本人であれば当然知っているものでした。しかし、第二次大戦の戦後処理の過程で、こういった古き良き日本人の素養が失われてしまったのは、悔やまれるべきことです。
「型」が確立しているからこそ、世代を超えて伝承していきやすい、そんな文化が日本には他にもたくさんあります。
和歌は、五・七・五・七・七の31文字の中で、枕詞や序詞、掛詞など厳格なルールを守りつつ、深い気持ちや情景を表現しなければなりません。また、リズム感のある構成となっているため、声に出して読むときは歌うように節を付けます。
藤原定家が選んだ100首の和歌を、上の句・下の句に分けて読み札・取り札とした歌がるたが「小倉百人一首」です。上の句に節をつけて読み上げ、下の句の札を取り合って遊ぶことにより、身体を使って習得していくことができます。和歌を丸暗記するのではない工夫があったからこそ、現代まで伝わってきたのでしょう。
ドイツの哲学者ニーチェは、著書『ツァラトゥストラはかく語りき』の中で、肉体そのものがひとつの大きな理性であり、精神は肉体の道具の一つでしかないと語っています。西洋哲学の世界では、このことが大きな発見だとされましたが、日本人にとっては古来から当たり前のことだったのです。
教養がある人なら、上の句を少し発声すれば、その歌を続けることができるはずです。耳から覚えたものなので、自然と節もつけているでしょう。かつては日本人共通の教養であるとも言えた百人一首ですが、今すらすらと諳んじることができる人は少数派かもしれません。
身体に「型」を刻み込ませるという、日本の教養の大きな柱が失われようとしています。読書で得られる知識や教養だけではなく、身体で継承する伝統や文化を、今こそ再評価するべきです。
NHK Eテレの人気番組「にほんごであそぼ」では、上方落語の「寿限無」や平家物語、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」など様々なジャンルの名文を、能や歌舞伎をはじめとする伝統文化の第一人者がわかりやすく表現します。
乳幼児でも楽しめる内容となっており、番組を観た子供達は名文の一節を暗唱することができるようになるのです。
幼い頃から美しい日本語や伝統的な文化に、身体を通して触れていくことにより、「型」として取り込んで行く、そんな経験をより多くの子供達に与えることで、日本らしい精神と型の文化を伝えて行きたいものです。
教養を「技」として使いこなせると、可能性が広がる
繰り返し刻み込まれた教養は、その人の「技」になる
知識も身体の奥深くまで刻み込まれ自分のものになると、「型」と同じように、いつでも思いのままに、その知識を使いこなすことができるようになります。最初は頭に入れた知識でも、教養として身体に染み込ませると自分の「技」となるのです。「技」も「型」と同様に、何度も稽古を重ねたり、繰り返して頭に叩き込む努力があって初めて手に入ります。
剣道や空手など、日本古来の武道だけでなく、茶道、華道そして書道などのお稽古はすべて「お手本をまねる」ことを繰り返し、身に付けて行きます。昔から日本人は、教養を身につけるために、外国語でも書道であっても、よきお手本をひたすら、自分のものにできるまでまねてきました。
料理人や職人の世界も同じです。言葉や書物で教えるのではなく、師匠の動きを目で見て、まねるというやり方で、技術を伝承していきます。これが日本の伝統なのです。
稽古を重ね、教養を身に付けた人が尊敬されたかつての日本で、特に教養のバロメーターとして「書き文字の美しさ」が重要視されていました。美しい文字を書くことは、教養以前に日本人としての素養でもありました。書の稽古では姿勢を正し、文字の意味は考えずに、精神を集中させて、お手本を見ながら繰り返し書きます。素読と同じ要領です。
歴史上の偉人はもとより、昭和の政治家の書く文字は非常に美しく、教養の深さがにじみ出ていましたが、現代はどうでしょうか?
社会的地位が高くても、文字が子供じみていて、書の素養がない人も増えてきました。一般の人に至っては、スマホやパソコンの普及とともに、文字を書く習慣が薄れ、鉛筆の正しい持ち方や漢字の書き方もあやふやな人がいます。
文字は書ければいいのではなく、書く姿勢や精神の統一、そして美しい書体を習得することが大切な教養だとされてきた、日本の文化は危機に瀕していると言えましょう。
身に付いた「技」を使いこなせると新しい価値が創造できる
ここまで日本の伝統であった「型」や「技」を身につけない人が増えてしまった原因は、戦前、戦後の日本の教育の違いに求められます。戦前は、書道、そろばんなど「型」を身につけるために反復練習を行う教科が多くありました。また、暗誦できるまで文章を音読するなど、身体に知識を染み込ませる教育方法が採用されていました。
教わった知識を暗誦できるようになると、自分の「技」となり、身に付きます。そして、身に付いた教養は、思い通りに使いこなすことができるようになります。例えば、落語家にある演目の一場面をリクエストすると、すぐさま演じることができます。自分の血肉となるまで繰り返し稽古を重ねたからこその「技」だと言えます。
また、落語家はなぞかけも上手です。お題を出されると、すぐになぞかけを返してくれるので、聞いている方は「さすが!」と感心します。なぞかけは落語家の本来の仕事ではありませんが、洒落をきかせた言葉遊びであるなぞかけと落語の共通点は多く、数多くの演目が身体に刻み込まれ、言葉の引き出しを多く持つ落語家の得意分野であると言えましょう。
教養を深め、様々な「技」を身につけると、その技を利用して新しい価値を創造するパワーが生まれてきます。基本となるものが身体の一部になっていれば、表現の選択肢が広がってくるのです。
逆に言うと、教養として知っておくべきことが、身体にとりこまれていないまま創作活動を行っても、底の浅い作品しか生み出すことができません。例えば小説を書く場合でも、新しい作品を創造するためには、過去の名作を読み、自分の中に取り込むことで、小説の「作法」を身につける必要があるのです。
教養の入口は「知っている」という状態です。その次のステップに上がると「知っていて、引用することができる」ようになります。身に付けた教養を自在に駆使して新たな価値を創造するという、「技」が身に付いた状態というのは、教養の最高峰であると言えるでしょう。
「すごい!」と感じたら徹底的にまねをして、自分の技にしてみよう
日本人は、知識を詰め込むのを相変わらず得意としています。しかし、時代の流れとともに、精神的に強靭で、芯のある日本人像が消え失せようとしているのではないでしょうか?これには、教育の変化が大きく影響しています。
寺子屋で行われていた「素読」や「禅」、そして「剣術」は教えを身体に叩き込むことによって精神も鍛えられるものでした。一方現在の学校教育では、「国語」「体育」と細分化したことによって、身体に「型」や「技」を刻み込ませるという、日本古来の教養がバラバラにされてしまいました。
今や伝統的な工芸や芸術の世界が中心となってしまいましたが、日本の文化は「模倣の文化」でした。それはただまねをする、といった単純なものではありません。お手本とすべき師匠の技を、じっと眺めて、同じようにやってみて、そして自分の技とすべく身体に刻み込むのです。「模倣の文化」は日本人の強みでもあったはずです。
「書」でも「そろばん」でも、稽古を重ねて自分の中に技が刻み込まれると、大きな自信になります。自分の中に一本太い柱ができ、心の安定も得られます。現代の日本人が、この激動の時代を生き抜いて行くためには、身体の中に教養という柱をたてることが必要です。
伝統文化や古典知識でなくてもかまいません。スポーツでも、ITやロボット技術など、これから世界のビジネス界で中心となっていく分野でもいいでしょう。知的好奇心をくすぐられたものに「すごい!」と感嘆の声を上げることができたら、自分のものにできるまで徹底的に勉強してみましょう。
更新日:2019/11/29|公開日:2017/12/05|タグ:教養