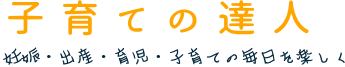卵子提供や代理出産をどう捉えるか?
最近では医学の進歩とともに不妊治療にも新しい技術が導入され、さまざまな形での妊娠や出産が可能になってきています。なかでも第三者から卵子を提供してもらった上での妊娠・出産や、自分たちの受精卵を他人に代理で出産してもらうといった事例も出てきています。ここではそうした事例について少し詳しく見ていきましょう。
卵子提供による出産とはどういったものか
女性が高齢で出産する場合、卵子の質が落ちていることによって流産の危険や染色体の異常などさまざまなトラブルが起きる可能性が高くなります。
この問題を解決するために、まだ質の落ちていない若々しい卵子を利用することで妊娠・出産を試みるというのが、卵子提供による出産の根っこにある考え方になります。
普通ならば高齢出産となり卵子の質が落ちているかもしれない45歳ぐらいの女性が、25歳ぐらいの妊娠適齢期にあたる女性から卵子の提供を受け、そこにパートナーの精子を体外受精させることによって受精卵を作るわけです。そしてその効果には著しいものが見られます。
卵子提供の技術を使えば、子宮さえあればたとえ50歳の方であっても妊娠することができます。受精のために必要な卵子は他人からの提供ですから、閉経しているかどうかも無関係になります。
卵子提供については日本産婦人科学会では禁止されておらず、法律の方の整備もなされていません。代理出産については学会のガイドラインで禁じられています。このため、卵子提供による出産や代理出産などが行われるとマスコミなどが大きく報道してきました。
例えば2006年に、子宮を摘出してしまって妊娠・出産ができなくなった30代の女性が、自分の卵子と夫の精子を使った体外受精を行い、できた胚を実の母(50代)の子宮に戻す形で代理出産を行い話題になったようなケースです
このケースでは長野県の産科医が体外受精を行ったわけですが、学会のガイドラインは守らなかったものの法律に違反したわけではありませんでした。この件に関しては学会内外問わずさまざまな批判や擁護意見などが飛び出し、たいへん大きな議論となりました。
とはいえ、卵子提供による出産というのは何一つ問題がないというわけではありません。そのうちの最たるものは、卵子提供者に肉体的な危険性がふりかかる可能性がぬぐえないということです。
卵子提供者に発生しうる危険とは
提供するのが精子である場合、提供する人には特に危険はありません。体や精神にかかるストレスもそんなにはないと考えていいでしょう。しかし、提供するのが卵子の場合にはそういうわけにもいきません。
卵子を提供する場合、提供する人に排卵誘発剤を注射することになります。しかもそれは1回打って終わりというわけではなく、1週間~10日という長期間にわたります。排卵誘発剤を打つと卵巣が刺激されて排卵が促され、1回で15個程度の卵子を採卵することになりますが、この採卵に際しては麻酔も使用しますのでそういった意味での危険性もあります。
このように、卵子の提供には肉体面での危険が避けられず、また長い時間拘束されてしまうためか、アメリカなどでは卵子の提供そのものがビジネス化しています。卵子バンクに登録して卵子を提供すると代価がもらえるのです。
例をあげると、日本人がアメリカで卵子を1回提供すると、だいたい60万円ほどの報酬を得ることができます。このため、アメリカに留学している女性の間にはバイト感覚で卵子を提供する方もいるそうです。
また、インドやタイといった国では、わざわざ渡航費を支払ってまで日本の女性を国に招き、卵子を提供してもらうことさえあると言われています。
このように、卵子を提供することで報酬を得ることができるのは、そもそもアメリカやインドやタイといった国に渡航して卵子の提供を受け、体外受精によって妊娠を試みる人が増加しているからだといえます。
卵子提供を受けて妊娠するのは確かに受け手の自由かも知れませんが、それでも知っておいた方がいい事実というのはあります。それは、海外で卵子提供を受ける場合に被る危険性です。
特に合理主義が幅をきかせるアメリカで顕著なのですが、アメリカの医師は妊娠させることを目的に据えるあまり女性の子宮に胚を複数個戻すようなことを平気で行います。移植を受ける人の年齢や状況など一切お構いなし、といった感じです。
もともとアメリカでは、40歳を過ぎた方が体外受精を望む場合には第三者からの卵子の提供を受けることを勧められることが多くなっています。これに対して日本の女性は何とか自分の卵子での妊娠をと望み、ぎりぎりまで不妊治療を受けた上で年齢的にいよいよになってからアメリカに渡航して卵子の提供を受けようとしがちです。
40歳も後半に入ったような方が卵子を提供してもらうことになるわけですが、そういった人に対しても妊娠の成功率を上げるために複数の胚を戻すようなことをするわけです。確かに成功率は上がるかもしれませんが、その結果多胎妊娠が起きることも少なくありません。そして、高齢での多胎妊娠は普通よりもかなり危険なものになりがちなのです。
日本での卵子提供をとりまく環境
今までは、日本においてはまだ若いにも関わらず排卵が起きなくなったような女性に対し、血縁関係のある姉や妹、あるいは知人などから卵子を提供してもらった上での体外受精というものは例がありました。
日本国内で卵子の提供を扱っている団体としては、2015年6月時点で国内の27の医療機関により構成されたJISART(日本生殖補助医療標準化機関)というところがあり、国内のでの体外受精のおよそ1/3強を手がけています。
この団体では倫理面での審査を厳密に行った後で卵子の提供を受け、それによる体外受精を行っています。こちらの審査はかなり厳密に行われているため、卵子提供を受けての体外受精に至るケースはかなり少なく、2007年以後でまだ二十数例しかありません。
また、2013年の1月には神戸市にある卵子提供登録支援団体(OD-NET)が、卵子を無償で提供してくれるボランティアを募り始めました。こちらの団体ではボランティアでの募集ということで、JISARTよりも広くドナーを募っているようです。
しかし、こちらの団体も、卵子の提供を受ける側には制限を設けています。たとえばターナー症候群を持っている方のように生得的に卵巣の機能が下がっている方であったり、早発閉経が起こってしまい若年にも関わらず無月経となり、卵子がないような女性に限っているのです。
また、提供をする側は子どもをすでに持っていてかつ35歳未満でなければならず、提供を受ける側は40歳未満である必要があります。
このように、日本で卵子の提供を受けるのは難しく、アメリカのようにその意志がある人が費用を負担すれば誰でも可能であるのとは対照的になっています。
OD-NETにボランティアとして参加する人の数はけっこうな人数になっているといいますが、これから出てくる問題として卵子の提供者に何かがあった場合、どのように補償を行っていくかの制度作りを行う必要があるという点が上げられるかと思います。
OD-NETによれば、卵子を採取するときにトラブルが生じ、健康に問題が発生したような場合は治療費が支払われることにはなっています。しかし、体調の悪化のために就業できず、会社を休んだような場合についての不利益に対する補償のような面まではまだ取り決めがないようです。
なお、日本に限らず、アメリカで卵子を提供する場合であってもこういった危険性は変わりません。排卵誘発剤を体に入れたことで体にトラブルが発生し、最悪入院を余儀なくされることもありえるのです。
卵子提供の意義と問題点
昨今、日本では高齢での妊娠・出産がどんどん増加してきています。そしてそれに合わせるようにして、40歳を過ぎてから体外受精を試みようとする方の数も増えてきています。
高齢での妊娠・出産はうまくいかない可能性がかなり高く、このため体外受精を何度も試みても失敗するというケースが多いわけですが、これは妊娠適齢期というものを知らなかったために起きていることだと言えるでしょう。
しかし、適齢期の知識を持たなかった女性を一方的に責めるのは間違っていると思われます。社会全体や国が少子化に対する対策を先延ばしに来たことや、女性に対する知識の普及がなされてこなかったという側面も大きな影響を与えているのは間違いないからです。
現在高齢の女性で卵子提供による妊娠・出産をしたい方は、基本的には海外に渡航した上で卵子の提供を受けています。これには馬鹿にならない費用がかかります。例えばアメリカで治療を受ける場合では、渡航費、治療費、仲介役のエージェントへの支払いなどで250万円は軽くかかると言われます。
こういった現状は明らかに問題があります。体外受精の技術そのものが上がり、卵子を採取する時に女性にかかる負担や危険が低く抑えられるようになったことと考え合わせれば、日本でも高齢の女性が卵子提供による妊娠・出産ができるように制度その他を整備するときが来ているのかもしれません。
一方で、国内で卵子提供が手軽に受けられる環境ができることにより、本来ハイリスクで避けた方がいい高齢での妊娠・出産を安易に選択する人が今よりも増えてしまうのではないか、という危険もまた併せて考えねばなりません。母親となる女性、そして生まれてくる赤ちゃんにとってより大きな不幸を招き寄せてしまう可能性があるということも忘れてはならないでしょう。
日本では高齢女性が養子をもらうのも難しい
年齢が上がり、体外受精などの最新技術を使っても妊娠・出産に大きなリスクを抱えるようになった女性たちが、そのリスクをあえて冒して海外に渡って卵子の提供を受けるという現況の背後には、卵子提供を国内で受けるのが難しいという直接的な原因の他にもさまざまな要因が潜んでいます。
たとえば、自分で子どもを産むことにこだわらず、身寄りの無い子どもを施設から引き取って育てる養子について見てみましょう。
野田聖子議員は2010年にアメリカに渡って卵子提供を受け、夫の精子で体外受精をした上で長男を出産されました。このニュースは一時期かなり報道されたのでご記憶の方もあるかと思います。
野田議員は45歳まで不妊治療を行っていましたが、その途中で養護施設から身寄りの無い子どもさんを引き取って養子にし、自分の子どもとして育てようと検討したことがあるといいます。
野田議員は生まれてからまだ1年にも満たない赤ちゃんを養子にしたいとある施設に申し出たそうです。しかし、それに対する答えは素っ気ないものでした。施設側は、野田議員の年齢が高齢であること、そして仕事をしていて専業主婦になれないといったことを理由として斡旋を拒んだというのです。
野田議員のケースに限らず、日本では養子が欲しいという人に対する斡旋の制度が時代の流れに追いついておらず、養子を取ってもいいと考える人の門戸を狭めているといわれています。
そうした斡旋団体では女性が40代になると高齢であるとみなし、養子の斡旋を断ることが多いと言われています。定年が65歳まで延長されるようになった時代にも関わらずです。
子どもさんが引き取られた後に不幸にならないように、と慎重になる姿勢は悪いことではないと思いますが、本当に子どもが欲しい方を事情によらず門前払いするような制度には問題があると思わざるを得ません。
養子をとりたいという方に対する選択肢がもっと選びやすくなれば、女性本人にも赤ちゃんにも危険な高齢での妊娠・出産を無理に行う人も減ってくるのではないかと思われます。
卵子提供ならば遺伝上のつながりはなくとも我が子と感じられる?
日本では卵子の提供が認められず、治療を受けたい方は外国に渡航して治療を行っているのが現在の実情です。その一方、非配偶者間人工授精(AID)というものは認められています。
非配偶者間人工授精は、配偶者である男性に不妊の原因があるような場合に、第三者から精子の提供を受けて受精卵をつくり、それを子宮に戻すという人工授精の形態のことです。
非配偶者間人工授精や卵子提供による人工授精の場合、養子とは違って少なくとも夫婦どちらかの遺伝子だけは受け継がれることになります。非配偶者間人工授精で生まれた子どもは遺伝子としては母親のものだけを受け継ぎます。それとは逆に、卵子の提供を受けて生まれる子どもは父親の遺伝子だけを引き継いで生まれます。
卵子提供による人工授精の場合、女性の遺伝子は引き継がれませんが、それでも母親となる女性は自分の子宮をつかってお腹を痛めて子どもを出産することになります。このことが子どもを出産する女性に及ぼす影響はけっして軽いものではありません。
卵子提供の場合自分の遺伝子は子どもに受け継がれてはいないものの、自分のお腹で赤ちゃんを育て、そして痛い思いをして産んだ子供であれば、女性は遺伝子のつながりがなくてもその赤ちゃんを自分の子どもだと思うことができると考えられます。
子どもにどのように真実を告げるのか
卵子提供の場合には、子どもとの遺伝上のつながりがなくとも母親となる女性は自分で赤ちゃんを育むことで赤ちゃんを我が子であると感じることができると思いますが、非配偶者間人工授精の場合にはそうはいきません。
というのも、第三者から精子の提供を受ける非配偶者間人工授精では、父親となる男性は赤ちゃんとの関係性において完全に無関係な位置に置かれてしまうからです。卵子提供で子どもを産む女性の場合とは異なり、男性は長期間の妊娠をするわけでも産みの苦しみを味わうわけでもないためです。
こうした理由から、専門家の中には非配偶者間人工授精は卵子提供などに比べて倫理的な問題を大きくはらんでいると指摘する方もいます。
日本においても60年以上の実績がある非配偶者間人工授精ですが、最近になって非配偶者間人工授精にまつわるある問題点がクローズアップされるようになってきました。親になる夫婦ではなく、夫婦の子として生まれた子どもが自分の産まれた事情について真実を知る権利についての問題です。
現行の制度では、非配偶者間人工授精で提供される精子については匿名という形で提供が行われることになっています。最近になって、大きくなった子どもが真実を知った際に本当の父親を知りたいと望むようになり、そうした望みにどのように相対するかという問題が起きてきているのです。
今まで父親だと思っていた人物と自分の間に実は血のつながりがなかったというのは、その子どもにとっては大きな衝撃です。遺伝学上の父親が別にいるということ、そして、そのことをはじめから教えてくれなかったということによる二重の衝撃を受けることになるのです。
こういったことが社会問題化する背後には、非配偶者間人工授精で子どもを授かった夫婦が子どもに対してその事実を告知しにくい、ということがあるかと思われます。
このように、非配偶者間人工授精などによる出生にまつわる事実を子どもに教えるというのは日本のみならず欧米でも難しい問題として持ち上がっています。子どもにこうした事実を分かりやすくまた衝撃を与えずに教えるのは本当に難しいのです。欧米で非配偶者間人工授精に関してかみ砕いて教えるような絵本が数多く売られているのは、この難しさを反映したものだと思われます。
英語圏で、子どもの出生に関することを子どもに教えることは「telling」という言い方をします。この表現はかなり最近になって使われるようになったもので、これは最近になって問題が明るみになってきたということを示しています。
子どもに対する告知はやはり難しいようで、欧米においてもおおよそ5%~10%程度のケースでしか告知がなされていないという調査結果があります。自分の子どもには非配偶者間人工授精を行ったという事実を知らないでいて欲しいと両親が考えているということです。
日本の病院で非配偶者間人工授精を扱っているところでも、将来的に子どもが自分の遺伝上の父親を知る権利が認められる場合に備え、精子の提供者についての情報を保管しているようなところもあります。
また、厚生労働省などが精子の提供者に対して行った調査結果によれば、子どもが遺伝上の父親を知りたいということについては、およそ2/3の方がそのような考え方があるのは仕方がないとし、2割弱の方が子どもにとっての当然の権利であると回答しています。
しかし、匿名であっても子どもと会いたいかという質問に対しては、実に9割近くの方が会いたくないと回答したのは興味深い点です。また、精子を提供して産まれた子どもが会いに来る可能性があったら精子の提供を行わなかったか、という質問に対しても、およそ2/3の方が提供しなかったと回答しています。
その理由としては、現在の自分の生活や家庭などに問題が起きる、といったものや、その子どもに対してなにがしかの責任を感じてしまう、といったものがありました。
こういった問題は、欧米ではすでに社会問題化してきており、たとえばスウェーデンやオランダなどでは子ども側の知る権利を認めてから精子を提供する人や非配偶者間人工授精を行おうという人が減っているといわれます。
こういった告知に関する問題は、卵子提供の場合は比較的軽いようです。非配偶者間人工授精を行った場合よりも卵子提供を受けた場合のほうが、子どもへの告知をした率が高いという調査もあります。実際にお腹を痛めて女性が子どもを産んだということが、肉体的・精神的な結びつきを強くするからではないかと考えられます。
仮に両親が子どもに告知をしていなかったとしても、その子どもが遺伝学上の親に会いたいという意志を示した場合にはその権利は擁護されなければなりません。
これから海外で卵子の提供を受けて体外受精を試みる方は、自分たちと産まれてくる子どもの間に将来こういった問題が持ち上がる可能性がゼロではないことを念頭において欲しいと思います。その上で、自分たち両親以外に卵子や精子を提供した遺伝上の親がいることを子どもに告知してあげる必要はあるのではないかとも考えられます。
代理出産と法律の壁
代理出産では卵子提供の場合などと異なり、男性と女性が自分自身の精子と卵子を用いて人工授精を行い、できた胚を他の第三者の子宮に移植して出産してもらうという形をとります。
最近で有名なケースとしては、芸能人の向井亜紀さんのケースかと思います。妊娠中に子宮頸がんであることが分かった向井さんは妊娠の継続を望まず子宮を摘出しました。本来ならばそれ以後の妊娠・出産は不可能になるところですが、採卵できた自分の卵子で人工授精を行い、それを米国人の女性の子宮に移植して代理出産をしたというものです。
この場合、遺伝子的には赤ちゃんには卵子と精子を提供した本来の両親のものが受け継がれていますが、卵子提供の時とは違って女性が妊娠や出産といったことに関わることはなくなります。
日本の国内法においては、赤ちゃんを出産した女性がその子どもの母親であるとされています。このため、出生届を提出する際に問題が発生します。
実際、先の向井さんのケースでも問題が発生しました。このケースでは2003年に双子の赤ちゃんが誕生したのですが、日本に戻ってから品川区役所に出生届を出そうとしたところ受け付けてもらえなかったのです。
結局この届け出は不受理となり、行政訴訟が行われることになりました。一審では敗れ、二審では出生届を受理するようにという判決が出ましたが、最高裁で出生届の受理は認められないという判決が確定しました。
こうしたことが起きるのは、代理出産が可能になるといった医学の進歩に対して、日本の国内法の法整備が追いついていないからと考えられます。
向井さんのケースでは親子の間に遺伝子上の血縁関係があるにもかかわらず、法的には親子として扱うことができないという形になっていますが、一方で民法第772条には、結婚している妻が妊娠した場合、遺伝子上の血縁関係が不明であってもその子どもは夫婦の子供であると推定するという規定があります。
現代では遺伝子検査のような医学技術が進歩しており、その子供が本当に父親の血を引いているのかといったことを科学的に知ることができるにも関わらず、昔作られたままの規定がそのまま運用されているためにこうした奇妙なねじれが生じているのです。
向井さんの裁判では、最高裁の判決でこのあたりについて法整備が必要だという判断も下されました。代理出産の是非はともかくも、どのようにして親子関係を認めるのかという点については急いで法を見直して欲しいと願う人も多いと思います。
代理出産は良いのか悪いのか
言うまでもなく代理出産という行為そのものに対しては賛成意見と反対意見があります。
たとえば、代理出産を利用することを迫られるのは、子宮にがんができるなど病気で子宮を摘出してしまっている女性や、産まれた時点で最初から子宮がなかった女性、あるいは妊娠や出産の際のトラブルによって子宮を摘出せざるを得なくなった女性などです。
賛成意見を唱える立場としては、このような人にも子どもを持つ権利があるという考え方をするようです。
反対意見を唱える立場としては、妊娠・出産の際にトラブルが起きて子宮を摘出するといった危険を経験した女性が、その危険を認識しながらも他の人に自分の子どもを産んでもらおうという考え方がひどく自分本位なものであり、倫理面での問題を避けられない、といった考え方があります。
確かに、代理出産というのは妊娠や出産に関わる危険性を自分以外の他者に負わせる行為です。危険を負う相手がそのことを了承した上でとはいっても、自分の子どもを得るために他人に大きな危険を負わせるというのは倫理面でも実際の面でも問題を引き起こしかねないと思われます。
代理出産は日本では認められていませんが、海外では代理出産が一種のビジネスになっている国もあります。そしてそのすべてのケースで何事もなくことが進んでいるわけではなく、数多くの問題が発生しています。
例えば、代理出産で産まれた赤ちゃんに生まれつきの異常があったという理由で赤ちゃんの引き取りを拒んだといったようなケースや、代理母が妊娠・出産の過程で命を落としたといったようなケースです。
その他にも、出生前診断をしたところ赤ちゃんに異常が認められたので中絶手術を強要したり、多胎妊娠していることが分かった時点で減数手術(複数の胎児から1人を選び、それ以外の胎児を死亡させる手術)をしたといったような事例もあります。
また、日本の現行法においては、代理出産で産まれた子供は遺伝子上の親の子どもとは見なされない(あくまで産んだ人物の子どもと見なされる)という点も、代理出産について考えるときには忘れてはならない点だと思います。