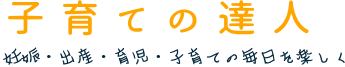不妊治療の実像!自分自身、親族、友人、… のために知っておこう
不妊治療の6つの基本検査、不妊治療の効果やリスクについて見ていきたいと思います。もし自分自身とは無関係だとしても、子どもができずに悩んでいる親族や友人が、もしいた時のために、この機会にきちんと理解しておきましょう。
基礎体温の測定から判明するさまざまな異常
不妊治療を行いたいと考えて産科に来られた患者さんに対して一般的に行われる基本の検査としては、
・基礎体温測定
・精液検査
・子宮卵管造影
・超音波断層検査
・頸管粘液検査
・フーナーテスト
といったものがあります。
基礎体温を計測する場合には、起床時に婦人体温計を用いて口内の体温を測るというやり方で行われます。これを毎日繰り返して記録を取り、わずかな体温の変化を見るのです。
一般的に、生理のサイクルは25日から38日程度で、月経自体は3日から7日程度続きます。
1回の月経と次の月経の真ん中ぐらいに排卵が行われますので、排卵してから月経が来るまでは約2週間ていどのスパンがあります。逆に言えば、最後に月経が来た日の2週間ほど前が直前の排卵日だったということになります。
前の月経があり、排卵日が来るまでの間は、基礎体温を測定すると少し体温が下がっていることが分かります。具体的には36℃程度になっていることが多く、これを低温相といいます。逆に排卵日の2日ないし3日後あたりから体温が少し(おおよそ0.3℃ほどです)上がる時期に入ります。こちらは高温相といいます。
このようにして日々基礎体温を測って記録することで、わずかな体温の変化が分かるようになります。たとえば低温相から高温相に切り替わったあたりで排卵があったということを予測できるので、妊娠の確率を上げることができるのです。
一方、基礎体温の記録を見れば、排卵にトラブルがあった場合にそれに気づくことができるようになります。低温相と高温相の差が見られず体温が同じ状態が続くようであったり、分かれていたとしてもサイクルが長くなっているような場合には排卵に異常が出ているかもしれません。
ストレスであったり体重が減ってしまったことにより、月経血は出ているにもかかわらず排卵が行われない無排卵性月経といった現象が起きることもあります。基礎体温をきちんと記録していればこうした状態にも気づくことができます。
基礎体温の測定や記録は毎日行わないと意味がありませんので、面倒だということで行っていない方も多くいらっしゃいますが、こうした月経の異常の他にも病気の早期発見にもつながります。
また、自分の月経のサイクルをきちんと把握することも大事です。これがきちんとできていれば、月経はまだなのに出血が起きる不正出血に気づきやすくなります。不正出血は子宮の病気、例えばポリープや子宮筋腫、子宮体がん、子宮頸がんといったものによって起きることがあるので、そうした病気の早期発見につながることがあるのです。
精液検査でわかること
不妊治療で行われる基本の検査のうち、精液検査では男性側の精子がどうなっているかをチェックします。男性側に原因があって妊娠がうまくいかないケースというのは、不妊全体のうちおよそ30%~40%程度あるとされています。
精液に精子がいない無精子症、濃度の低い乏精子症、運動率の低い精子無力症などのほか、精子に奇形があったりするような場合があり、これらが1つだけでなく併発していることもあります。
このうち、仮に乏精子症であった場合、では自然な形での妊娠が不可能かといえばそんなことはありません。乏精子症は一回に射精される精子の数が少ないというだけですので、自然妊娠でも人工授精でも妊娠自体は可能なのです。
卵子は女性の体の老化とともに質が低下していくことが分かっていますが、精子の方はそうしたことがはっきりと裏付けられた研究はありません。男性の体が老化すると共に精子濃度が下がっていくという傾向はありますが、加齢が生殖細胞に及ぼす変化という点では女性の卵子の方がより著しいのです。
女性の場合40歳を過ぎると自然妊娠する可能性はがた落ちしますが、男性の場合精子の濃度が低い場合や60歳や70歳であっても妊娠につながる可能性があり、中には90歳で子どもを授かった、といった例も報告されています。
これは、卵子の場合は産まれたときから新しく作り直されることがなく、数も質もどんどん落ちていく一方なのに対して、精子は他の細胞と同様に毎日新しいものが作られていることから起きてくる差です。毎日作られているので質が下がりにくいわけです。
また、精子は卵子を受精させる際に数億分の1単位での競争が行われるため、たとえ質の低い精子が混じっていたとしてもそうしたものは卵子にたどり着けず、質のいい精子が卵子を受精させる可能性が高くなる、といった事情も影響しています。
一方で卵子の方はこういった競争・淘汰がほとんど働きません。1回の排卵までに育つ卵子は一度に5つから7つ程度で、その中から1個の卵子が主席卵胞として選択されて排卵されます。つまり、こちらの競争は10分の1にも満たないわけです。
このような点から見て、精子の方はある程度の濃度があり、かつそれなりの運動率さえあれば妊娠面にそんなに大きな影響は及ぼさず、逆に卵子のほうが妊娠できるかどうかに大きな影響力を及ぼす、ということが言えるかと思います。
不妊治療に関して行われる基本的な検査
不妊治療で行われる基本の検査のうち、子宮卵管造影、超音波断層検査、頸管粘液検査は女性の体の方をチェックするものです。
子宮卵管造影では、特別な器具を使って子宮口に造影剤を入れ、子宮から卵管へと造影剤がどのように流れていくかをレントゲンを使って見るということを行います。このようにすることで卵管が詰まったり癒着していないかを見ることができます。そのほかにも子宮腔や子宮自体に問題はないか、子宮内膜にポリープやアッシャーマン症候群がないかなどもチェックすることができます。
アッシャーマン症候群というのは子宮内膜で炎症が発生し、そのために内膜が萎縮して癒着してしまう症状です。この症状が起きると内膜が成長せず、胚が着床することが不可能になってしまいます。原因としては中絶や流産の歳の手術、あるいは出産後の胎盤の処置を行った時に子宮が傷ついたり何かに感染することによって起こります。
アッシャーマン症候群が発見される人は案外に多く、不妊症の女性の1%~2%ほどにみられますが、最近では抗生剤が進歩したことなどによって減ってきてはいます。
超音波断層検査というのは超音波を使って子宮や卵巣を見てチェックする検査です。お腹の中の胎児の状態を見るエコー検査と基本は同じです。超音波断層検査では子宮自体に問題がないかや、子宮内膜の厚みなどをチェックする他、卵巣自体に問題がないか、そして卵巣内の卵胞がいくつあり、どれぐらいのサイズであるか、といったことも検査します。
頸管粘液検査では、膣と子宮をつなぐ子宮頸管という部分について見る検査で、排卵日近くに行われます。
子宮頸管は、排卵がおきる前に頸管粘液と呼ばれる粘液でいっぱいになります。この粘液には精子が子宮に進入するのを助ける働きがあり、もし分泌されていなかったりすると精子が子宮まで到達できないといったことが起きかねません。頸管粘液検査では、そのようなトラブルが起きていないかをチェックすることになります。
フーナーテストと呼ばれる検査は不妊治療を行う男性と女性が性交を行った3時間~12時間後に行います。頸管粘液や子宮腔内にある液体を吸い取り、その中にどれぐらいの数の精子がいて、またどれぐらい運動性があるのか、ということをチェックします。
吸い取った液体の中に精子がいて運動していることが分かれば、子宮腔まで精子が届いていることが分かります。精子が届いているか届いていないかによって治療のやり方を考えるわけです。
このようないくつかの基本検査による情報を下敷きに、それ以降どのように治療を行っていくか、ということについて決めていくことになります。
不妊のメイン治療法――人工授精と体外受精
本格的に治療に入る前に基本的な検査を行い、治療の方針が決まったら実際に不妊治療に入るわけですが、そうした不妊治療のメインとも言える治療法に人工授精と体外受精というものがあります。
人工授精というと何かものすごく不自然なことをするのではないか、といった印象を受けるかもしれませんが、実際に行うことは自然妊娠の時とそんなには変わりません。
精液の濃度が少なくて精子数が少ない場合や、精子の運動率が少し低いような場合、普通に性交を行っても精子が子宮腔まで到達できず、途中ですべて死んでしまうことがあります。そういった問題がありそうな場合、この人工授精を行い、人間の手で直接精子を子宮まで入れるということを行います。
人工授精の施術は排卵日に行われます。最初に男性から精子を採り、それを遠心分離することで運動性の高い精子だけを選びます。そしてそれを濃縮した後で注射器を用いて子宮に直接注入するというやり方を取ります。一度に注入される量は0.5ミリリットルほどです。
つまり、人工授精というのは精子と卵子を直接的に受精させるというものではなく、精子を卵子に近づきやすい状態にしてやるという発想で行われるものです。
もう1つの治療法である体外受精は1978年に初めて成功した技術で、この技術が使えるようになってから不妊治療の現場は劇的に変わりました。
体外受精では、排卵近くの卵巣に細い針を刺し、卵巣から卵子を採取します(これを採卵と言います)。採卵した卵子はシャーレに取られ、そこに精子が振りかけられます。これによって受精が起きれば受精卵として細胞が分裂し始めますので、問題なく分割が進むことを確認した上でそれを女性の体内に戻してやるのです。
受精卵は分裂して胚になっているわけですが、この胚を戻すのは受精成立後3日から6日ほどの間に行われ、チューブに入れて子宮の中に注入するという形で行われます。この時戻される胚のサイズは0.1ミリメートルほどとなります。
その後7日~10日ほどたってから女性の血液の中のHCGホルモンの数値を測定します。HCGホルモンは妊娠検査薬が妊娠しているかどうかの判定をする際にも使われており、血液中の値を見ることで子宮に戻した胚が着床し妊娠が成立しているかどうかを知ることができます。
このほか、1992年に初めて成功した技術として顕微授精というものもあります。顕微授精はものすごく細いガラス管を使って精子を1匹吸い取り、顕微鏡を使いながら卵子にガラス管を刺し、直接精子を中に入れてやるという方法です。顕微授精は区分としては体外受精の1つということになります。
人工授精や体外受精の違いについてチェック
人工授精や体外受精について、どれぐらいの費用が発生するものなのか、そしてどれぐらいの確率で妊娠に成功するものなのかを見てみましょう。
まず費用的な面ですが、人工授精と体外受精を比べると圧倒的に体外受精の方が高くつきます。人工授精は1回施術を受けるとおおよそ1万円から2万円といったところですが、体外受精の場合には1回施術を受けると40万円~60万円ほどかかることもあるほどです。
体外受精の場合、施設によっては1度目がうまくいかなかった場合には次からは値段が下がったり、採卵、受精、着床といった各段階ごとに費用が増額されたりと価格体系もさまざまな場合があるため一概には言えないのですが、それでも人工授精よりは間違いなく高くなります。
次に有効性について見てみましょう。人工授精の場合、妊娠できない理由が男性側にあるケースにおいては割合効果が上がることが多いようです。
精液の中に精子が入っていない無精子症では、非配偶者間人工授精と呼ばれる手法で受精を試みます。これは第三者にあたる男性が提供した精液を用いて女性の卵子と人工授精を行うものです。
また、男性が性交の際に勃起することができないようなケースにもかなり有効です。性交時は勃起しないがマスターベーションはできるといった場合には、精液自体には問題がないことが多いので、男性の精液を取って女性の子宮に入れてやればそのまま妊娠にこぎ着けることができることが多いのです。
さらに、人工授精と体外受精を比較すると、女性側の負担が人工授精の方が圧倒的に少ないという点もポイントかと思います。人工授精では排卵日付近で男性の精液を採り、それを女性の子宮に注射すればそれで施術が終わりますが、体外受精ではそう簡単ではないからです。
体外受精ではまず女性の卵巣から採卵し、それを受精させた後に子宮の中に戻してやらねばなりません。その後無事胚が着床した後もホルモン療法などを続ける必要があるため、約半月ほどは通院が必要となるなど、肉体的な負担に加えて時間的な負担もそこそこのものになってくるのです。
このように見てくると人工授精の方が不妊治療として良さそうに思えますが、最大の違いとして妊娠の成功率があります。1回の施術による妊娠率の平均を見ると、人工授精が3%~5%程度である一方体外受精では20%~30%に跳ね上がります。これだけ成功率に差があるとなると、費用や負担の度合いだけで選ぶかは簡単に決められないかと思います。
顕微授精は有効性が高い
不妊治療においては、人工授精よりも体外受精の方が平均妊娠率が高いため有効性は高いのですが、体外受精のうちでも顕微授精はいろいろな場合に高い有効性を持っています。
顕微授精というのは、採卵までは体外受精と同じ手順を踏みます。すなわち、排卵が近いた時期の卵巣に細い針を刺し、卵巣から卵子を採る形です。その上でものすごく細いガラス管を使って精子を1匹吸い取り、顕微鏡を使いながら卵子にガラス管を刺し、直接精子を中に入れてやります。
採卵した卵子に精液をかけて受精を試みる方法とは違って、正常な精子が一匹いるだけで受精・妊娠ができるようになるため、男性側に問題があって不妊になっているような場合にはかなり効果が高い治療法となってきます。
さらに、顕微授精では卵子の質が下がっているような場合でも受精ができるようになるというのも特徴です。
加齢によって卵子の質が下がっているような場合、顕微鏡で見たときに一目でそれが分かるような状態であることがあります。質のいい卵子は卵と言うだけあってきちんと円形をしているのですが、40歳ぐらいの女性から採った卵子の場合形が変わってしまって歪んでいたり、卵子を構成する細胞質内にぶつぶつしたものができていたりといったことがあるのです。
卵子がこういった状態だと、たとえ体外受精を行ったとしても受精に至ることはほとんどありません。このため不妊治療を行う場合には、なるべく形やきれいで、色がよくて透明感の高い卵子を選んで精子を入れることになります。
あるいは、卵子の質が下がっている場合、卵子の周りを覆っている殻が分厚くなってしまっていることがあります。こういった卵子の場合精子が中に入ることが大変になってしまうため受精につながりにくくなってしまいます。しかし、顕微授精を行えばこの殻を針で突き通して直接中に精子を入れてやることになるため、受精する可能性が出てくるのです。
こういった特徴があるため、体外受精や顕微授精といった手段をとるとかなり受精しやすくなり有効性が高いのですが、不妊治療を望む方の間で体外受精に対して抵抗がある方が多いというのもまた事実です。
不妊治療で体外受精について説明を受けても、抵抗が払拭できないために体外受精を行わず、人工授精止まりになる方が多いのです。
不妊治療を行う際の主役はあくまで患者であり、医師が人工授精にすべきか体外受精にすべきか決めるということはありません。ですから体外受精に抵抗を感じるのでそれを選択しないというのも立派な決断です。しかし、体外受精や顕微授精を行った方が妊娠の確率が増えるのに、というような患者さんたちがいるのもまた事実ではあるのです。
体外受精なら必ず子どもが授かる?
不妊治療の中でも体外受精は有効性が高いわけですが、それでも1回の妊娠率を平均すると約20%~30%ほどとなり、施術を受ければ必ず妊娠できるという性質のものではありません。しかし最近、こういった体外受精の限界についてよく知らず、体外受精さえすればどんな人でも必ず妊娠できるかのように誤解している人がおられるようです。
産科によっては不妊症の治療をしたいと考える人たちのために正しい知識を伝える不妊学級であったり、体外受精について知ることができる体外受精学級のようなものを開催しているところがあります。
そういったところに参加される方、つまり一定程度妊娠や不妊症の治療といったことに関心のある方であっても、中には妊娠のメカニズムや適齢期を知らなかったり、体外受精の限界について知らなかったりする方がかなりの割合でいるのです、
そのように聞くと妊娠や出産についての意識が低い男性側がそうなのか、とお考えになるかたもあるかもしれませんがそうではなく、女性すらそうだというから驚きです。加齢とともに卵子の質が落ちるという事実や、適齢期に妊娠できないと妊娠自体が難しくなる、といった基本的な知識を知らなかったり、あるいは体外受精をするとかならず子どもが授かるという誤解をしているような方がたくさんいらっしゃるのです。
体外受精をすれば母親が高齢であっても問題なく赤ちゃんが産めるという誤解を持つ方は、特に2000年ごろから増えてきているようです。これは、日本産科婦人科学会による調査で高齢の女性が体外受精を受けるケースが目立って増えてきた時期と重なります。
日本産婦人科学会の調査によれば、体外受精した場合の妊娠率を見ると、女性の年齢が26歳~34歳までのケースでは妊娠率は約25%となっていますが、それよりも高齢になって行くにつれてこの妊娠率は逓減し、37歳付近で20%、40歳では15%を下回り、43歳ではなんと5%にまで落ち込むという結果が出ています。
これはあくまで体外受精を行った場合の妊娠率であり、無事出産までこぎ着けた割合はさらに下がります。26歳~36歳までは15%を超えていますが、39歳付近で10%以下となり、40歳で約8%、45歳になると0.5%にまで下がってしまいます。
この調査結果から見る限り、たとえ体外受精をしたとしても、女性の年齢が35歳を超えてしまうと妊娠率も無事出産にこぎ着ける割合も下がってしまい、必ず子どもが授かるどころかむしろ授からない場合の方が多いという結果が見えてくるのです。
排卵誘発剤の効き目と危険性
不妊治療を行うに当たっては、女性が高齢である場合には排卵誘発剤を使用するのが治療の基本的な柱の1つとなってきます。排卵誘発剤で卵胞が育つのを促進させるのです。
排卵誘発剤は、月経のサイクルが不順だったり月経がないようなケースの他、排卵に問題があることで不妊が生じている場合に使われますが、排卵には問題ない場合であっても不妊治療による妊娠の確率を上げるために使用されるケースがあります。
排卵誘発剤を使うと場合によって多胎妊娠(双子や三つ子の妊娠)が起きることがあるため、排卵誘発剤を利用したがらない患者さんもいます。実際のところ、多胎妊娠では妊娠合併症が起こりやすくなり、元気な子どもが産まれる見込みが下がってしまうため、こうした懸念を抱かれる方があるのは理解できます。
排卵誘発剤には大きく2種類のタイプが存在します。内服薬と注射薬です。このうち内服薬はクロミフェンといい、自然妊娠の場合に双子になる確率(約1%程度)が2%~3%程度に上昇します。影響によって多胎妊娠が起きた場合でも双子の場合がほとんどで、それ以上になることはあまりありません。
一方、注射薬はHMG・HCG製剤といい、こちらは多胎妊娠の確率が20%程度まで跳ね上がります。そのうち8割ほどが双子となり、三つ子や四つ子になる確率はそれぞれ15%と3%程度になっています。
排卵誘発剤、特に注射薬には多胎妊娠以外の危険性もあります。卵巣過剰刺激症候群(OHSS)と呼ばれる症状を起こしてしまうことがあるからです。
卵巣過剰刺激症候群では排卵誘発剤の効果が出すぎてしまい、卵巣の中で卵胞があまりにもたくさん育ち始めてしまいます。そしてその影響で卵巣が腫れてしまい、腹水がたまってしまったり、血液循環が悪くなってしまったりします。重傷になると入院が必要になってしまうこともあります。
注射タイプの排卵誘発剤は危険性も高いですが、内服薬タイプよりも妊娠率が上がるという点では優れています。排卵性効率を見ると、内服薬では約80%なのに対し注射では90%になりますし、妊娠率を見ると、内服薬では20%なのに対し注射では30%~50%といったように、明らかに効果が見られるのです。
排卵誘発剤による危険性については、それを利用した上で人工授精をするのか体外受精をするのかでだいぶ変わってきます。注射をした時点では卵巣過剰刺激症候群寸前ですんでいても、妊娠したことによって卵巣が腫大し症状が重くなってしまうといったことが起こったりします。
こういったケースでもし体外受精を行っている場合には、採卵した卵子が受精し、細胞分裂が始まって5日ほどたった「胚盤胞」という状態をいったん凍結することで保存します。
いったん胚盤胞と呼ばれる状態まで分裂を進めるのは、それ以前の状態の胚を戻すよりも妊娠や出産が成功する確率が上がるためです。そしてそれを卵巣過剰刺激症候群の症状が治まった頃に子宮に戻すといったことができます。このようにしても、凍結しない状態の胚盤胞を戻したときと妊娠や出産が成功する確率が変わらないからです。
もっともこの胚盤胞を戻すやり方にも危険性はあります。そもそも体の外で受精卵を胚盤胞まで育てること自体が難しいというものです。卵子が受精してから胚盤胞まで細胞分裂を進めることができるのは、体の外という環境ではよくて60%程度とされています。
しかし、卵子を採った時点で卵巣過剰刺激症候群になるリスクが高まっている場合、受精した卵子をすぐに戻してそれを誘発するよりも、いったん保存しておいた上で次の月経のサイクルまで時間をおき、卵巣の腫大がおさまってから胚を戻すということができる点、疾病リスクを下げることができます。
さらに、日本産科婦人科学会では、体外受精をする場合に多胎妊娠になってしまわないように、一定の指針を発表しています。
それは、受精卵を移植する際には原則1つしか戻さないものとし、母体が35歳以上であったり2回以上連続して妊娠が成立しなかったような場合には2つまで戻す、というものです。この指針が出て以降は体外受精を行った場合の多胎妊娠はめっきり数が減り、国外、たとえば欧米などに比べて日本では多胎妊娠になる確率がかなり低めに押さえられています。
しかしこれは体外受精の場合で、排卵誘発剤を使った上で人工授精をする際には多胎妊娠の問題を抱えたままになっています。体外受精とは違い、人工授精では排卵誘発剤で排卵が促された状態の子宮に精子を注入することになるので、体外受精の時のように受精卵の数を制御するということができないからです。
このため、排卵誘発剤を使った上での人工授精では体外受精の際よりも多胎妊娠が起きる危険性が上がってしまいます。万一卵巣内で卵胞がいくつも成長してしまった際には、多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群などの危険を避けるために誘発剤を使うのを中止し、排卵自体を中止させるといった処置をとることもあります。
低刺激療法の光と影
排卵誘発剤を使うと場合によって多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群を引き起こしてしまうという危険性があることから、近ごろでは体外受精を試みる際に卵巣を刺激する場合に、加える刺激を少なくとどめる低刺激療法といったものが盛んになりつつあります。
この低刺激療法というのは、自然なサイクルを利用したり内服する種類の排卵誘発剤を利用することで卵巣を刺激し、採卵を試みるというやり方です。
低刺激療法の場合、投薬は内服で行われますので通院する必要がないというのが利点の一つになります。また、卵巣に直接働きかけるのではなく、脳の視床下部という部分に働きかけて排卵を促すことになりますので、卵巣過剰刺激症候群がおきることもありません。
このように副作用や危険性が少ない低刺激療法ですが、一方で排卵数が2個~3個にとどまるという弱点も持っています。
高齢の方の不妊治療、それも40代ともなると、普通の卵巣刺激法でも卵子をたくさん得ることができません。卵巣に注射をするタイプの薬を用いても排卵がうまく誘発されないことが多いので、負担が減らせる低刺激療法を選んで排卵を試みることが増えてきています。
排卵誘発剤を投与される側の女性にとっても、効果が高い注射薬はそれだけ体にかかる負担も強く、どうしても通院が必要になってくるために仕事や生活との兼ね合いといった問題も発生してきますから、そういったデメリットの少ない低刺激療法は魅力的に映るのでしょう。強い誘発剤を使った場合卵巣過剰刺激症候群がおき、体外受精の機会が減る可能性もあるということならばなおさらです。
医師の側から見ても、低刺激療法による不妊治療はうまみが大きいため、患者に勧めたくなるのかもしれません。というのも、低刺激療法では体外受精を試みる場合でも通常の生理のサイクルにちかい形で採卵できることから、毎月1度採卵することができます。つまり1年で何度でも体外受精の施療を行うことができるため、いい収入になるというわけです。
低刺激療法は実際に自然な形に近く、女性の体への負担も少ないわけですから、医師が女性に勧めやすいという点もあるでしょう。女性側と医師の側の思惑が一致しやすいわけです。
とはいえ、注射タイプの排卵誘発剤を使うのがすべてダメかというとそういうわけではありません。そうしたタイプの誘発剤には問題はあるとはいえ、やはり妊娠率は高いのは間違いないからです。ですから、注射タイプの誘発剤と聞いただけで拒否するのではなく、選択肢の視野に入れておいてほしいと思います。
タイミング法も有効な治療法
不妊治療としては人工授精、体外受精、そして顕微授精というような手段がありますが、そのようなやり方を取らないもっとも基本的な治療方法としてタイミング法というものがあります。
タイミング法は最近ではもはや治療のカテゴリには入らないものと見なされつつありますが、だからといってその有効性が減少しているわけではありません。タイミング法を試すことで普通に妊娠できるといったケースも多くあるのです。
タイミング法では、最初にエコーを使って女性の卵巣を確認し、卵子が収められた卵胞の大きさをチェックします。エコーを使った確認で卵胞が18mm~20mmぐらいになっていたら、もう少しで排卵が起きるということですので、性交渉を行って妊娠を試みるべき時期が分かります。
タイミング法は、言ってしまえば基礎体温を計測・記録して妊娠のタイミングを計るのと基本的には同じですが、基礎体温によって排卵日を推測するよりもより確度の高い推測を行うことができるのです。
体外受精などを何度も試してうまくいかなかった方であっても、かかる産婦人科を変えてタイミング法から再度治療を行ったところ妊娠できた、といった例はいくつもあります。ですからあながち侮るべき治療法とも言えないのです。
このように、不妊治療を行って妊娠にこぎ着けたいという場合には、いきなり体外受精に飛びつくのではなく、まず検査をきちんとした上で3ヶ月~6ヶ月ほどはタイミング法での妊娠をきちんと試み、それでもやはり難しいということになった時点で人工授精や体外受精などにステップアップするというのがいいのではないかと思われます。
しかし最近の不妊治療の現場では、いきなり体外受精や顕微授精を試そうとする方が多くなってきています。これは女性の結婚自体が遅れてきているということも背景にあるかと思いますし、医療機関のほうでもそういった判断をすることが多くなってきているような傾向があります。
40歳を過ぎた女性が妊娠を希望する場合には、とにかく猶予がありません。比喩ではなく日一日と受精・出産の成功率が下がっていくわけですから、悠長にはしてられないというわけです。
医療機関のほうもそれが分かっているので、高齢での出産の希望があると医療機関側もすぐに体外受精に進みがちになるわけです。そして、事実としてもっと早く体外受精の試みを始めていれば……というような場合もたくさん見受けられます。
加齢によって卵子の質が落ちてくると、たとえプロである医師でなくても、素人目にも卵子の状態が悪いことが一目で分かるようなこともしばしばです。顕微鏡の画像を本人に見てもらった時点で、受精は無理なのではと分かってしまうレベルなのです。
仮にそういった卵子を使って無理に体外受精を試みても、やはり受精の成功率は低く、出産までこぎ着ける率もやはりかなり低くなってしまうのが普通です。
一方で、検査で見えた卵子がそんなに質が悪そうにも見えず、精子のほうにも問題がなさそうなのに受精に何度も失敗するようなケースもよくあります。こうなってくると、医者のほうでも原因が分からず頭を抱えるようなことになります。
妊娠率は上がるが流産の可能性も高い体外受精
体外受精は、人工授精に比べて明らかに妊娠率が上がります。人工授精が3%~5%程度なのに対し、体外受精では20%~30%であることからこれは明らかです。しかし、体外受精は万能ではありません。流産率も高いのです。
一般の妊娠で流産する確率はおよそ12%~15%ほどと言われています。これに対して体外受精を試みた場合の流産率はおよそ25%ほどとなり、なんと約2倍にも上るのです。
30年前に初めて成功した時から、体外受精で妊娠できるようになる技術のほうは年々進歩が見られるのですが、一方でこの流産の確率だけはほとんど変わりがありません。そして、明確な原因もまた分かっていないのです。
特に染色体に異常が見られる胚が増加しているということもないのに、原因不明なのです。ですから体外受精という技術はまだまだ研究途上と言えるかもしれません。あるいは、体外受精や顕微授精といった技術にはまだ解明されていない部分に技術面での問題があり、それがこうした流産率の高止まりという形で現れているのかもしれません。
ちなみに、体外受精によって誕生した場合、受精卵に人の手を加えれば加えるほど赤ちゃんの体重が増加してしまうということも知られています。たとえば、2007年~2008年度の2年間を例に取り、体外受精を行って出産予定日付近で無事産まれた赤ちゃん2万7千人の出生時の体重を見てもそうした傾向は明らかです。
体外受精を行って、そのまま受精卵をおなかに戻したケースでの出生時体重の平均値は3,003gなのに対し、受精卵を5日間培養し胚盤胞になった時点で戻したケースでの平均は3,025g、初期胚を凍結して保存したケースでは3,070g、胚盤胞に育った時点で凍結保存したケースでは3,108gとなっています。
このように、医学的な処置を加えれば加えるほど、赤ちゃんが生まれてくる時の平均体重は増加していっています。こうした調査結果に対しては、いまでもいろいろと調査検討がなされています。
なお、ゲノムインプリンティング異常症と呼ばれる、遺伝子の活動をコントロールするシステムに異常が発生してしまう病気があるのですが、体外受精を行った赤ちゃんにはこの病気が出やすいという研究結果もあります。
ゲノムインプリンティング異常症では、赤ちゃんが過度に成長してしまうという症状が出ることもあり、もしかするとこうした点が産まれてくるときの体重増加と関連しているのかもしれないとも言われています。
一方で、近ごろの傾向として赤ちゃんが低体重で生まれてくることが多くなってきていたことから、出生時に体重が増えてしまうこと自体はかえっていいのではないか、という意見もあります。
たとえば日本の赤ちゃんを例に取ると、産まれたときの体重が2,500gを切っている赤ちゃんが占める割合が、1975年ごろから右肩上がりで増え続けているのです。具体的に言うと、1975年の時点では産まれた赤ちゃん190万人のうち、5.1%が低体重児でした。これが、2009年には産まれた赤ちゃん107万人のうち、9.6%を占めるまでになっています。
それだけでなく、妊娠中に体重を増やしたくないと考える妊婦さんが増えてきたためか、妊娠している間に体重が増えた量も昔に比べて少なくなってきてるという調査結果があります。
最近では昔と違い、なるべく妊婦さんの体に負担をかけないために赤ちゃんを小さく産んで大きく育てるという発想での出産が増えてきていましたが、何事にも限度というものはあります。平均体重にして、20年で200gも赤ちゃんの体重が軽くなってしまっているのは明らかにやり過ぎではないでしょうか。
イギリスの疫学者であるデヴィッド・パーカー氏は、産まれたときの体重が少なすぎる子どもは、将来動脈硬化や高血圧、糖尿病などを発症する危険性が高くなってしまうという生活習慣病胎児期発症説という説を1986年に発表しました。
これが事実かどうかはともかく、出生時に赤ちゃんの体重が2,500g未満になってしまうようなことはなるべく避けるべきなのではないでしょうか。理想としては、赤ちゃんの体重は3,000g~4,000gほどあったほうがよいのではないかと思えます。
不妊治療の助成金
厚生労働省では、妊娠できない男女を対象として、不妊治療の助成金という制度を整備しています。これは特定不妊治療助成という助成金で、体外受精を1回行うにつき15万円が支給されるというものです。
助成金の支給回数には制限があり、1年目は年に3回まで、2年目以降は年2回となっています。支給される期間は全部で5年までで、最大10回まで支給を受けられるという制度です。つまり、10回とも利用すれば合計150万円の助成金が支払われることになります。なお、この制度を利用するためには所得制限があり、夫婦あわせて730万円以下の家庭に限られます。
この助成金の利用状況を見ると、一番最近の調べでは1年に112,642件のケースに助成金が支給されていて、支給額を合計するとおおよそ170億円に上ります。この助成金の原資は我々の支払った税金ですから、これだけの税金が不妊治療に利用されていることになります。
この助成金を利用している夫婦数は増加していない一方で助成されている金額の総額は増加しています。高齢での出産を希望する夫婦がこの助成金を利用するケースが増えているために、助成を受ける回数が増えているものと考えられます。上限となる10回まで助成金を利用するケースが珍しくはないのでしょう。
現実を見ると、妊娠する女性の年齢を考慮に入れない場合であっても、10回あるいはそれ以上におよぶ体外受精を経て妊娠・出産できるというのは非常にレアケースです。その手前、8回・9回でうまくいく確率もかなり低く、体外受精がうまくいく場合には3回以内で成功するということが多くなっています。
日本の不妊治療に特徴的なのは、35歳という妊娠適齢期を超えた後から不妊治療を開始する方がたいへん多いという事実です。30代前半で不妊治療に入られる方の数はものすごく少なく、全体の60%程度は30代後半、中でも38歳から40歳の方が中心群を形成しています。40代以上の方もけっこう見られ、およそ30%程度にのぼります。
2012年の6月にNHKで不妊治療に関する特集番組が組まれましたが、そこで調べた調査によると、米英独などの先進八カ国で体外受精を試みた方のうち、40代の方は日本のおおよそ1/2ないし1/4しかいなかったということです。例えば米国では、不妊治療を試みる年齢の中心群は36歳~38歳となっています。
女性の体が加齢するにつれ卵子もまた質が落ちていくのですが、そのスピードは35歳から40歳の5年の間にぐっと上がります。このため、35歳を過ぎてからの不妊治療は1年でも1ヶ月でも早いほうが成功しやすくなります。そういった観点から見ると、米国と日本における不妊治療の年齢が2年違うというのは、成功率的にはかなり大きな違いとなって現れてくるものなのです。
先輩ママさん5万人調査!臨月、出産期に産後に備えて買ったものランキング
更新日:2019/11/29|公開日:2015/04/13|タグ:不妊治療