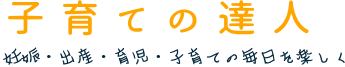発達障害を極める!
発達障害は比較的年齢が低いころに現れ始め、行動、コミュニケーション、社会適応に対して問題を持つ障害を指します。発達障害の中には広汎性発達障害、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、知的障害といったさまざまな障害が含まれます。
こうした障害はそれぞれにさまざまな特徴を持っており、表面に現れる症状や障害の内容、あるいは能力面なども個人ごとに大きく差がでてきます。発達障害について詳しく見ていきたいと思います。
診断が難しい発達障害
発達障害は次のような形で分類されています。
1.広汎性発達障害:さらに自閉症やアスペルガー症候群などに分類されます。社会性や他人とのやりとりの能力、想像力などに障害があるものです。
2.注意欠陥・多動性障害(ADHD):注意力や集中力に欠け、また衝動的で感情の制御が難しいといった特徴を持ちます。
3.学習障害(LD):特定種類の学習に大きな困難を伴いますが、知的な遅れはありません。
4.知的障害:年齢に即した知的能力に欠けます。自立には支援が必要となります。
幼児の発達障害は診断を下すのが難しい
発達障害は脳の機能や情報伝達の機能に障害や問題があることが原因とされていますが、感覚面での障害や衝動的に行動してしまうといった点で共通する部分もあるために、患者が幼い場合には正しい診断名をつけるのが難しいという側面もあります。
このような診断の難しさにより、患者である子どもに即した治療や教育を早期に開始することが難しいというのが実情です。
幼少時から発達障害があることは分かっていたものの診断名がころころ変わり、5歳ぐらいになってようやく例えばアスペルガー症候群である、といったように症状名が決まるといったようなこともままあります。アスペルガー症候群は広汎性発達障害の一種で、自閉症と共通する症状も多く、社会性や他人とのやりとりの能力、想像力などに障害を持っています。この例のように子どもがアスペルガー症候群であると分かれば、それに対する適切な治療や養育方法を採ることができるわけです。
子どもが幼い場合、こうした診断を付けることはより難しくなります。例えば自閉症の場合、幼い時には不安を感じると泣いて暴れるといった行動を取ることもあり、そのために注意欠陥・多動性障害であると診断されることも多いといいます。
また、親と一緒にいるときには特に問題行動は取らないのに学校に行くと症状が出るといったようなこともあります。このように子どもの成長度合いや状況によって症状に変化が出るケースでは、その子どもの病気を正確に見極めるのはなかなか難しいのです。
アメリカのカンザス大学による調査によれば、発達障害を持つ子どもに正しい診断名が確定するのは、アメリカでは平均で9歳頃であるとされています。多くの場合、親や周囲の大人のいうことを聞き入れなかったりルールを守らないといった症状が出る反抗挑戦性障害であったり、躁と鬱の状態をいったりきたりする双極性障害、あるいは広汎性発達障害など、4つから5つほどの異なった診断結果が出ることが多いようです。
脳の測定による診断も研究されている
発達障害の子どもたちの診断名を早く確定するため、脳そのものに着目しようとする研究があります。
例えば、注意欠陥・多動性障害の場合については特殊な方法で脳を測定することによって診断に利用する試みが進められています。カリフォルニアのダニエル・エイメン医師は、SPECT(単光子放射型コンピュータ断層投影法)を利用することで診断に利用しようとしています。
SPECTでは放射性物質を用い、脳の中の血液の流れや脳の活動を測定することができます。健康な人の脳であれば、ものごとに集中したときに前頭皮質の活動の度合いが高くなります。前頭皮質は注意の持続や衝動を抑える機能がある部分です。対して注意欠陥・多動性障害を持っている人の脳では、集中しようとすると前頭皮質の活動度合いが下がり、安静にすると活動度合いが上がるということが分かったのです。
ダニエル医師は、SPECTで数千人ぶんの脳の活動を調べ、その結果に基づいて注意欠陥・多動性障害を診断したり、薬の効果が上がっているかの判定をしたりしています。
日本においても、奈良県立医科大学の飯田教授の下で、注意欠陥・多動性障害の人の脳の研究が行われています。注意欠陥・多動性障害の患者の脳では情報処理プロセスで障害が起こるという点に的を絞り、脳の注意機能が現れる「事象関連電位」という脳波を調べているのです。
片方の耳から連続した音を聞かせ、もう片方から断続的に刺激音を聞かせる実験を行うと、刺激音を聞かせたときに現れる脳波の振幅が、健康な人よりも注意欠陥・多動性障害の人の方が小さくなるという現象が見られます。飯田教授はこの点についての研究を進め、将来的に障害の診断を正確に行えるようにしていきたいとしています。
また、自閉症についても研究が行われています。ノースカロライナ大学のヘイゼル・コーディ助教授は、自閉症を持つ子どもの脳と健常者の脳との比較を行っています。研究の結果、自閉症を持つ子どもの脳においては、1歳~2歳の間に大脳皮質のうちの頭頂連合野と呼ばれる部分(言語に関連している部分)が、健常者の脳よりもおよそ5%ほど大きくなることが分かりました。ただし、脳を測定するだけで自閉症の診断ができるようになるまでにはまだ至っていません。
診断分けが難しい発達障害
ある人が発達障害であるかどうかを見る際には基準があります。これは、アメリカの精神医学会から出ている「精神疾患の診断統計マニュアル第四版」(DSM-IV)と呼ばれるものです。
このマニュアルでは発達障害の診断には厳格な基準が設けられています。例えば広汎性発達障害は優先的に診断されることになっていて、ある人が広汎性発達障害と注意欠陥・多動性障害を同時に発症しているといった診断は許されていないなどです。
これに対し、現場の医師たちからは、複数の障害が重なり合って起きているような症例が見られるということで、このマニュアルに定められた厳格さに疑問の声も上がっています。自閉症と注意欠陥・多動性障害の双方の症状が見られるような場合があったりして、両方の疾患に対する対策をしなければいけないような事例もあったりするためです。
このため、マニュアル通りに厳格に診断を下すのではなく、患者本人の状態に見合った対応を取ることがまずは大事になってくるといえます。
さまざまな形で分類されている障害について、その境目をどこに定めるか、あるいは障害どうし重なり合っているような部分は存在するのか、といったテーマは、国際的にも議論の対象となっています。
今までの考え方では、広汎性発達障害のカテゴリの中に自閉症やアスペルガー症候群が含まれるとされてきました。しかし最近では、知的障害が見られる重症の場合と、知的水準が高いような場合とを併せて、自閉症というものを連続したやり方で捉え直す自閉症スペクトラムという考え方も提唱されています。
また、アスペルガー症候群と自閉症にはいずれも感覚障害という共通した症状があります。このような共通した症状というのは割合に多いため、それぞれの障害に通じた専門家どうしが知識を持ち寄り、それを共有していくことで患者に合わせた効果の高い治療や養育方法が見いだせるはずだとする専門家もいます。
自閉症
自閉症は、社会性の障害や他人とのコミュニケーション能力に障害が出たり、特定のものごとに強いこだわりがでたりする精神障害で、広汎性発達障害の一種です。最近教育の現場では自閉症が見られる子どもが増えているとされます。その障害の特徴などを見てみましょう。
アメリカで進む自閉症児サポートプログラム
自閉症を発症した子どもは、社会性や創造力、他人とコミュニケーションを取る能力という3つの分野に障害を持っています。自閉症は、知的障害を伴っている場合と伴わない場合(高機能自閉症)とがあります。
自閉症の子どもは変化に適応することが得意でなく、対人面で感情的な交流を取ることが難しく、抽象的なものの考え方が理解しにくいという特徴を持っています。このため、自閉症の子どもにとっては家庭生活や学校生活は理解が難しい出来事の連続になってしまう傾向があります。
アメリカのノースカロライナでは、こうした自閉症の子どもたちを総合的にサポートするために「TEACCH」と呼ばれる教育・療育プログラムが設けられています。ノースカロライナ大学医学部には自閉症を専門的に研究しているTEACCH部が設けられており、付属の施設として州内9カ所に自閉症センターがあります。
こうした施設では年間およそ千組ほどの親子が訓練を受けます。他人とのコミュニケーション能力を高めたり、抽象的なものの考え方について理解を深めたりするのです。
そんな親子の中に、高機能自閉症(知的障害のない自閉症)の障害を持ったAちゃんがいます。Aちゃんはこの施設にやってくるとお母さんや保健師さんといっしょに塗り絵をしたり、描かれた絵について前や後ろといった抽象的な概念の理解に努めたりといったことを行っています。そうした訓練の様子は施設の臨床心理士などが観察し、観察結果を研究に生かしたり親にフィードバックしたりしているのです。
Aちゃんは抽象的な概念の理解が困難で、例えば塗り絵で色を塗っている猫の部分が前なのか後ろなのかがよく分かりません。前に顔がついている方が前と教えてもらったことを思い返して、自分の顔を手で触りながら確かめ、やっと猫の顔がある方を「前」と答えたりします。生き物以外のもの、例えば椅子といったものについては顔がないのでこの方法が使えません。このため、椅子のどちらが前かを尋ねると戸惑った顔をします。「前」や「後ろ」といった考え方を一般化することができないのです。
また、Aちゃんはものの形や色彩といったような具体性のある質問には特に問題なく答えを返すことができますが、自分の考えていることや要求ごとを周りの人にどうやって伝達したらいいかが分かりません。このため、例えば塗り絵をしているときにあれこれ質問されると、突然動きを止めて凍り付いてしまったりします。色を塗るという作業もしたいし質問にも答えたいということで困りきってしまい、最終的には椅子や机の下に隠れてしまったりします。
理解しにくいものは「構造化」する
TEACCHとは、“Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”のそれぞれの頭文字をとった造語で、「自閉症及び関連するコミュニケーション障害をもつ子どもたちのための治療と教育」という意味になります。
ノースカロライナ大学の医学部に設置されている自閉症児研究チームが60年代に立ち上げたもので、自閉症を持つ人が社会の中で有意義に、できるだけ自立して暮らし行動できるようサポートすることを目的にしています。
TEACCHでは実際に自閉症を有している子どもたちを観察し、自閉症という障害の特性を理解することを理念として掲げています。それぞれの能力に合わせたサポートや療育を与えることによって、患者の自立を支えようと取り組んでいます。
TEACCHでは、教室の中について、そこを(学習、遊び、教育といったように)何に使うのかといったことで色分けしたり、時間や目的をはっきりさせた表を作って自閉症の子どもたちに伝達したりします。
また、自閉症の子どもにとっては理解しにくい時間という考え方も、何か課題が終了するたびに箱の中にボールを入れてみせるといったような具体的な形で見せるようにしています。こうしたやり方は「構造化」と言われています。
自閉症の子どもの意思をどう伝えさせるか
自閉症を持っている子どもは、表面に現れる症状からひきこもりと間違われたり、他人との関係を構築できないといったような誤解を受けがちですが、多くの場合友達など他の人と接触を持ちたがります。このため、自閉症患者が他の人と相互に理解し合えるように、考えていることを相手にどう伝えるかの手段を開拓することも必要だとする立場に立つ専門家もいます。
自閉症の子どもの中には言葉を使ったコミュニケーションよりもより視覚的に情報を処理することを得意としているような人もいます。こういった子どもにとっては、言葉を使うよりも絵や文字を使ったコミュニケーションのほうがやりやすいのです。
そういった子どもに有効なのがカード式のコミュニケーションです。たとえばカードに「ヘルプ」と書いたものを自閉症の子どもに渡し、親など周囲の人に助けを求めるための訓練に使ったりします。
言葉のコミュニケーションが苦手な自閉症の子どもは、たとえ親に対しても「やめて」「助けて」が言えないことが多いのですが、こうしたカードを使って練習をするうちにきちんと自分の意思を他人に伝えることができるようになっていくといいます。
「ヘルプ」のカードをきっかけに、母親が自閉症の子どもと接するときに子どもに伝えたいことに写真や絵をつけて説明することで、子どもとの意思疎通がよりはかれるようになった、という事例もあります。
TEACCHではこうしたカード式の成果を生かし、携帯情報端末を利用した実験を行っています。
高機能自閉症を持った高校生の子どもたちに端末を持たせ、端末を操作すると「にっこり笑って」「相手の目を見て名前を呼んで」「自分ばかり話し続けないで」といったように、相手とのコミュニケーションを円滑に進めるための注意がそこに表示されるようにしたのです。端末を持つようになった子どもの多くは、他人と意思疎通をしてみようという様子を見せるようになるといいます。
アメリカにおける自閉症児の包括教育とは
アメリカの小学生・中学生の間では、相手に対して親しみを表すため、「よう、ワン公」などとわざと罵り言葉で挨拶を交わすことが流行っています。普通の子ども同士であればこれは特に問題にはなりませんが、自閉症の子どもを相手にこうした言い方をした場合には話が違ってきます。
自閉症の子どもには特有の認知方法があり、かけられた言葉を額面通りに受け取ってしまいます。このため、こうした罵り言葉で挨拶されたときに相手が悪意を持っていると解釈してしまうのです。
アメリカでは自閉症の子どもの教育に関しては選択肢が多く、自閉症の子どもを専門に扱う学校があったり、親が自分の子どもを自宅で教育するといったこともできます。
しかし最近では、言語面や知的な面に問題がない場合には、一般の学校に通わせて必要になったら特別教育を受けるという包括教育というスタイルがメインになってきています。たとえば最初の例のようなことが起きたときには、自閉症の子どもに対して子どもどうしの間で行われているコミュニケーション慣行などを個別に教えるのです。
しかしこうした包括教育の場でも、一般の生徒と同じ教育を受けることが自閉症の子どもにとっての訓練となるというふうに単純に考えるのは間違っています。ボディー・ランゲージなどの言語によらないコミュニケーションを理解する能力であったり、抽象的な概念について理解できていなければ、友達が冗談や親しみを込めた言葉をかけたのにそれを誤解してしまうといったようなさまざまな問題に発展しかねないからです。
とはいえ、自閉症を抱える子どもも社会でやっていくためには他人とのやりとりであったり社会性といったものを学んで身につけなければなりません。包括教育はそのための場としては一番適切な場であるとは言えるでしょう。
普通の教師たちにも研修を
自閉症の子どもに対する包括教育を行うには、それまでは自閉症の子どもとあまり接してこなかったような普通の教師たちも自閉症についての正しい知識を身につけ、特有の認知のやり方であったり社会性の面で遅れが生じているといったことを学ばねばなりません。
通常の学級に参加しているとは言え、自閉症を持っている子どもは他人とのやりとりが不得手であるため、場合ごとに正しい対応方法を学ばないと相応しく行動できない、といったことがあるからです。
こうしたことから、TEACCHでは毎年研修や集中講座を行って教師を目指す学生や教師たちを啓発しています。研修は精神医学、教育学、福祉学などを学んでいる学生を対象としたものになっており、また集中講座についてはノースカロライナ州の教師たちのうちおよそ1/3が受講を済ませているといいます。
日本における状況は
自閉症の子どもの場合教育上の必要性が多岐にわたることから、アメリカではその子どもが入園したり入学したりする前にIEPと呼ばれる個別の教育プログラムを作成します。これは教師、医師、作業療法士などの専門家がチームを組んで競技を行い、その子どもの障害の度合いであったり、教育のやり方や指導方法などを検討して作られるものです。
一方日本においても、最近教育の現場で自閉症が見られる子どもが増えているとされています。例えば横浜市などが行った調査では、平成4年以前に生まれた子どもの間での自閉症の発生割合は1万人あたり47~85人だったのに対し、平成5年以降に生まれた子どもの間では1万人あたり96~161人というように明らかに増えているのです。
日本の場合、高機能自閉症や注意欠陥・多動性障害(ADHD)といった発達障害を持つ子どもの割合は、一般学級の児童の中のおよそ6%を占めるという調査結果があります。しかしこうした子どもたちは今まで障害児として見なされることはなく、これまでの特殊・進級学級においてはしかるべき指導を受けることができずにいました。これは、これまでの特殊・進級学級が視覚障害、聴覚障害、言語障害、あるいは肢体不自由といった障害を持つ子どものみを対象にしていたためです。
こうした問題を踏まえ、平成19年から特別支援教育制度が導入されました。この制度では、今までの特殊・進級学級が対象にしていた子どもたち(およそ17万9千人)に加え、発達障害を抱えている子どもたち(およそ68万人)が対象となります。
実際の教育現場では教職員の間からコーディネーターを選ぶなどの準備が行われています。このコーディネーターとは、療育施設・医療機関と学校、そして保護者の間に立って橋渡しを行う役割を持っています。
とはいえこうした準備はまだ始まったばかりで、また専門的な知識を持った教職員の数も圧倒的に足りないのが現状です。このため、川崎医療福祉大学の大学院でノースカロライナ大学と姉妹提携を行い平成19年にTEACCH部が開かれるなど、人材育成に向けた動きも出始めています。
アスペルガー症候群
アスペルガー症候群は広汎性発達障害の一種で、(1)他人と社会的関係をもつこと、(2)コミュニケーションをとること、(3)想像力と創造性といった3つの分野に関して障害が見られるという特徴があります。
アスペルガー症候群の患者は感覚に障害が生じることが多い
アスペルガー症候群では言語機能や知能の面では遅れが見られないため、自閉症の中でももっとも軽いもの、といった考え方をされてきました。しかし、最近になって、アスペルガー症候群を持つ人は多くの場合感覚障害を有しているということが分かってきました。
アスペルガー症候群の患者は感覚からもたらされる刺激に対して敏感であったり、あるいは逆に鈍感であったりします。こうした感覚障害は不快や不安といった感覚をかき立てるため、それが問題行動の引き金となったり、学習の際の妨げになったりします。アメリカにおいては、こういった特徴を持った子どもたちを対象にした特別教育が開始されています。
例えば、アスペルガー症候群を持っているある子どもは、ぱっと見には普通に見えますが、圧力嗜好という症状を抱えています。この子どもは体に何らかの圧力がかかっていないと落ち着かなくなってしまうのです。たとえば、靴を履くときには紐で足をぎゅうぎゅうに締め付けたり、足裏と足の甲をこすり合わせたり、眠るときに親の体の下に入り込んだりします。
アスペルガー症候群をはじめ、広汎性発達障害の患者はあるものごとや行いに対して強いこだわりを持っていますが、そのこだわりの原因の一部にこうした感覚障害があるのではないかとする報告があります。
アスペルガー症候群に見られる感覚障害には、圧力嗜好以外にも聴覚、視覚、味覚、嗅覚、温痛覚といった部分に問題が生じます。例えば聴覚に感覚障害がある場合、日常聞こえる普通の大きさの音であっても耳をふさいだりします。
アスペルガー症候群を持つ人の日常行動は、こうした感覚障害に対して少し配慮をしてあげることで楽になります。たとえば、聴覚過敏であれば耳栓を使わせる、視覚に問題があるならば少し暗めの部屋をつくる、といった具合です。
感覚障害はどんな原因で起こるのか
人間の体に備わっている感覚は、よく言われる聴覚、視覚、嗅覚、味覚、触覚、といった五感に加え、前庭感覚や固有感覚といったものがあります。前提感覚というのは平衡感に関わるもので、耳の奥にある内耳で自分が空間の中のどこに位置しているかを感じ取る感覚です。固有感覚というのは筋肉や関節といった体の動きを感じ取る感覚です。そして、これらすべての感覚を統合して調整を行うメカニズムも備わっています。
人工的にこうした感覚の一部を阻害することで、感覚障害に似た状態を体験することができます。たとえば迷路を解くときに普通に解くのではなく鏡に映した状態で解いてみたり、目にした風景が歪むように作られたプラスチック製の板を通してものを診ながら歩いてみるなどです。こうした経験をすると、普段とはまったく違った感覚に襲われるため、不快感や苛立ちさえ感じます。感覚障害を持つ人は常にそうした状態にあるわけです。
感覚障害については、選択的注意の機能(周囲からのさまざまな情報から今必要となるものだけを選び出す能力)が不完全であることが原因ではないかと考えられています。なお、アスペルガー症候群の患者にはこの選択的注意が不完全なケースが多くあります。
学校に通う時期の子どもにこの障害があると、ものごとに集中することが難しくなります。また、さまざまな情報の中から教師の声を選び出し、それに耳を傾けるといったことも難しくなるので、勉強が遅れてしまう二次的な障害が起きやすくなります。
ちょうど特定の食材にアレルギーを持っている人の食事から原因となるものを除去すれば問題なく食事ができるように、アスペルガー症候群を持っている人の周囲の環境からその人が不得手な刺激を除去した上で与える必要のある刺激を与えれば、問題行動や注意力不足は減っていきます。
感覚障害がどれぐらいの度合いであるのか、あるいはどんな特色があるのかといったことをきちんと評価できる基準を作ることができれば、そのようにして一部の感覚を除去したり与えたりすることがより効率的にできるようになってくるでしょう。
アメリカにおける学校ぐるみでの取り組み
アメリカのカンザス州では、小学校や中学校において、日々の活動の中で感覚統合の訓練をすることができるようなプログラムの導入が図られ始めています。
例えばコットンウッド・ポイント小学校では、「感覚の部屋」という名称の通級教室を設置し、感覚障害を持つ子どもたちを指導したり特別教育を行うときに利用しています。この教室の入り口にはプラスチックのビーズでできたのれんが下がっていて、光を反射するようになっています。また教室の中には小さなトランポリンやブランコ、乾燥させた豆の入ったプールといった器具が設置されています。
感覚障害などで長い時間じっとしていられないような子どもたちは、休み時間の間にこの教室に訪れ、こうした器具を使ってしばらく遊んだ後で授業を受けに教室に戻ります。また、教室においても授業に集中できるように、普通の椅子ではなくてゴムでできたボールに座って授業を受けたりするといいます。
感覚障害のある子どもの周囲から刺激を取り除いたり必要な刺激を与えたりした場合でも、それによって得られる効果はずっと続くわけではありません。人間の感覚はだんだんと状況に慣れますので、この学校では刺激を除去したり与えたりした効果がどれぐらいの間持続するのかを考え、子ども一人一人のための対応策を作成しているといいます。さらには、過敏になっている感覚になれさせたり、前提感覚や固有感覚を鍛えるための体操なども利用されています。
この他にも、アメリカでは体を適度に圧迫して刺激を与えることができる伸び縮みするアンダーウェアが普通に売られていたり、平衡感覚を鍛えることができる足が一本しかない椅子といったものも売られています。日本よりも感覚障害に対する注目度が高い現れかと思われます。
アスペルガー症候群にもさまざまなタイプがある
アスペルガー症候群の子どもと一般の子どもを比較し、感覚的な要因について調査すると、アスペルガー症候群の子どもは調査項目のほとんどすべてにおいて一般の子どもよりもかなり過敏な反応を示したり、あるいは反応が鈍かったりします。
また、口の中の感覚や触覚、あるいは前提感覚に問題を抱えている子どもは半数以上におよび、受けた感覚を処理するという部分で問題を持っている子どもは2/3ほどに上りました。
感覚の感じ方の程度や、必要とする刺激を自分から求める程度がどれぐらいかということを軸に、感覚障害は4つのグループに分類することができます。
どんな刺激が欲しいのかを自分の意志で表現できる子どもたちは周囲からみてもわかりやすく、従って対応が取りやすい一方で、自分の意志でそうした欲求を表現しようとしない特色を持つ子どもたちは感覚が鈍かったとしてもおとなしさとしてしか認識してもらえず、周りの人が障害を持っているということに気がつきにくい原因となります。
注意欠陥・多動性障害
注意欠陥・多動性障害(ADHD)は注意力や集中力に欠け、衝動を制御することが難しいという特徴を持った発達障害です。子どもがこの障害を持っていると、その子ども本人のみならず親や家族もかなりたいへんな思いをするといいます。
注意欠陥・多動性障害とはどんな障害なのか
注意欠陥・多動性障害の症状としては、じっと座っていられず周囲にちょっかいを出したり教室から出ていったりする、気が散りやすい、興味のないことを聞かない、約束してもすぐに忘れてしまう、順番待ちが苦手、手を使った細かい作業が不得手、空気が読めず暴言や不規則な物言いをして問題を起こす、といったようなものがあります。
注意欠陥・多動性障害は7歳ぐらいまでに発症します。だいたい幼稚園ぐらいから、みんなができることができない、といった形や問題行動ばかり起こす、といったような形で表に出てくることが多いようです。
この障害がどのような理由によって発生するのかについてはまだ明確に分かっていませんが、前頭葉の機能不全、ドーパミンという重要な神経伝達物質の不足またはドーパミンの受容体の機能トラブル、といった理由があるのではないかとされています。
小学校以上の子どもではおよそ6%程度が注意欠陥・多動性障害を発症しているという調査もあり、現れ方の特徴から親のしつけがなっていないであるとか、性格的に問題がある、といったような誤解を受けがちです。
そのため、問題を起こす本人ばかりでなく、親や家族も大きな悩みを抱え込むことがあります。学校から連絡されて何度も出向いたであるとか、家にいくつもお詫びの菓子折を用意しておいて、問題が起きるたびに相手方に謝りに行った、といったような苦労をされている家庭もあるといいます。
現在のところ、注意欠陥・多動性障害に対する治療方法は中枢神経を刺激する薬剤の投与しかありません。
それ以外の点でも、教育面や心理面からのサポートを与えつつ行動療法を行っていくことが不可欠となります。具体的には、障害のある子どもがいいことをした時にはすぐに分かりやすい形で褒めるようにしたり、良くない行動を取ったときにはあまり注目しないようにしてその行動が良くないのだということを子ども自身が気づけるように仕向けるといったようなものです。
何かをやり遂げた感じが障害児に変化をもたらす
注意欠陥・多動性障害の子どもはさまざまな問題行動やトラブルを起こしますので、一見すると傍若無人に見えますが、その実内心では自信をなくしていることが多いとされています。トラブルを起こしたことで親や教師に叱られたり、友達とうまくやっていけなかったり、勉強面でもトラブルを抱えたりしがちだからです。
このため、何かをやり遂げたという感覚を得ることができるようにサポートすると、そうした子どもたちは見違えたように集中できるようになったり、何かをしたいという意欲を見せたりするようになります。
平成13年、「大阪ADHDを考える会のびのびキッズ」という会が結成されました。この会には注意欠陥・多動性障害を持つ子どもがいる親や学校の教師などおよそ150人ほどが参加し、事例研究や子ども向け教室などを開催し、注意欠陥・多動性障害の子どもを抱える親や家族へのサポート、そして子ども本人へのサポートを行っています。
この会の子ども向け教室は集団での行動の取り方や他の人とどんなふうに関わりを持ったらいいかといったことを経験することができます。注意欠陥・多動性障害の子どもや自閉症の子どもたちが一緒に参加しており、遊びやゲームといった活動を通じてそうしたテーマを学んでいくのです。
こうした学びを通じて、障害を持っていて最初は順番待ちができなかった小学生が、自分よりも小さな子どもに順番を待つように教えたり、ものを借りるときには貸して欲しいというようにといったことを教えたりするようになるといいます。
また、この会では学校側にも働きかけを行っています。たとえば家庭科の時間などでは担当の教師と相談の上で裁縫をする際に針通しを準備したり、縫い目に色を付けて縫いやすくするといった工夫もしています。
そのほか、指を使うことで二桁の筆算ができるようになったであるとか、簡単な課題を用意すればリコーダーで音楽を奏でることもできるといったケースも見られ始めており、教える側がどんな態度を取っているかしだいで注意欠陥・多動性障害の子どもでもより高度な学習体験ができるという示唆が得られています。
診断をする際には注意深く
注意欠陥・多動性障害の現れかたには、大きく分けて次の3つの種類があります。
1.注意力や集中力に欠ける
2.多動性が見られ、衝動を制御することが難しい
3.上の両方の特徴が見られる
注意欠陥・多動性障害を持つ子どもは自閉症や学習障害、あるいは知的障害といった他の障害に見られるような症状を呈する場合もあり、教科書的に線引きして対応を取ることが難しいこともままあります。
注意欠陥・多動性障害かどうかを診断する場合にはアメリカ精神医学会が発表しているマニュアルが使用されます。注意力・集中力に関連している9つの項目に当てはまった場合、あるいは多動性や衝動性に関連している9つの項目に当てはまった場合、もしくはその両方の項目に6つ以上当てはまった場合は障害がある「可能性がある」ということになります。
子どもは肉体的にも精神的にも成長が早いため、こうした項目に当てはまったからといってすぐに注意欠陥・多動性障害であるとするのは早計です。その子どもが注意欠陥・多動性障害であると診断を下すためには少し時間を取って詳しく行動を観察する必要があり、診察室での挙動だけではなく学校での様子や家庭でどんな行動をするかといった点も調査すべきなのです。
その上で、仮に上記の基準に当てはまっていたとしても、日々の生活に大きく困難が伴うということがないのであれば、それは障害ではなくその子どもの性格だと考えるべきとされています。
障害を持っていると考えられる場合でも、子どもに言葉で話しかけ応答させたり、視認によって動作を行わせるようなさまざまな課題をさせてみて、外界からの刺激を処理してそれに対して反応をする流れのどの部分に問題を持っているのか、あるいはどういったやり方であればコミュニケーションが取りやすそうなのかを分析し、子ども1人1人にあったコミュニケーションの方法や接し方を模索していくべきでしょう。例えば、話しかけるよりもイラストを使った方がうまくいくのであれば、イラストをコミュニケーションに取り入れるようにするといった具合です。
注意欠陥・多動性障害は確かにハンデになりますが、裏返せば探究心が強く、創造力や行動力に富んでいるということもできます。周りの人が理解を示し、しかるべき対応を取ることが必要だと思われます。
注意欠陥・多動性障害はどれぐらいの割合で発症するのか
注意欠陥・多動性障害については調査する対象や診断の基準にばらつきがあるため、国ごとの単純な比較は難しいのですが、国別に発症割合を見るとアメリカで5%~7.5%、カナダで3.8~9.4%、オーストラリアで3.4%、ドイツで4.2%、中国で6%~9%といった割合が報告されています。国や地域による差はさほどないかわりに性差はあり、女子に比べて男子の方に多いという特徴があります。
日本の発症率を見ると、1クラスに1人か2人程度障害を有する子どもが存在するといった感じになります。そして発症者の性別を見ると女子1に対し男子4~7と男子に多い障害となっています。
なお、アメリカでの調査になりますが、障害を持っている子供のうち1/3は成人するころには障害が直っているとする研究結果も存在します。
学習障害
学習障害は、全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算、推論といった能力のうち特定のものを習得したり使ったりする際に著しい困難があるという特徴がある障害です。学習障害には早期に対応することが大事になってきます。
さまざまな現れを持つ障害
人間の脳は、司っている機能や部分によって前頭葉、側頭葉などという形でいくつかにカテゴライズされます。そしてそうした場所ごとに、感情、感覚、そして記憶といったようにコントロールする分野があると考えられています。
学習障害の原因は、こういった特定の部位に生まれつき何らかの障害があることだと言われています。学習障害の現れ方は人によってさまざまで、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するといった特定の分野について習得や使用する際に問題が出ます。
たとえば数の概念がうまく理解できず、年齢を尋ねられたときに5歳、と言いつつ指を1本だけ出してしまう、といった例や、ものごとについての順序の概念がうまく理解できず、文字版を並べ替えて「チョコレート」など意味のある言葉を作ろうとしても、「コョチトーレ」といった具合にどうしてもうまくできないといったような具合です。
こうした子どもたちは、知能全体では特に発達に遅れはないものの、ある特定の分野だけはどうしても習得・使用ができないという症状を呈します。
学習障害がどのようにして発生するのかについては詳しいことは判明していません。中には脳の形に異常が見られたようなケースもありますが、はっきりしたことは分かっていないのです。
日本にはこうした発達障害を持つ子どもや情緒面に障害がある子どもが教育・療育をすることができる施設があまりありません。独立型の児童精神科医療施設となると片手で数えるほどしかないのが現状です。
とはいえ、学習障害の場合脳の別の場所を使って考えるような訓練を早くから行うことでそれなりに障害がある分野の機能を補完することができるとされています。我が子に障害があると認めるのは容易ではありませんが、学習障害が疑われる場合には早期に対応することが大切です。
得意な分野を伸ばす教育も
学習障害の子どもはけして全般的な知能が低いわけではありません。むしろ、不得意なフィールドを除けば普通の子どもの平均よりも能力が高いということも珍しくないのです。たとえばアメリカの有名俳優であるトム・クルーズ氏は7歳ぐらいから読書に障害を持っていたといいますし、エジソンやアインシュタインといった偉大な科学者の中にも学習障害にあたる人物がいたと言われています。
このため、将来子どもが自立するためのことを考え、障害を持つ分野をなんとかして克服しようとするよりもむしろその子どもが得意としている分野を伸ばすようにした方がいいのではないかと考える親もおり、そういった人は公的な教育機関ではなく民間教育を選択することが多くなっています。
たとえば、名古屋にある見晴台学園は、学習障害を持つ子どもたちの保護者たちが平成2年に設立した施設です。学習障害を持つ子どもたちの教育に特化した施設で、日本ではたいへん珍しいといえます。
この施設では13歳~20歳までの生徒一人一人の能力にみあった個別の指導を採用しており、それぞれの習熟度合いに応じて別々の教材を作成したりして対応をしています。また子どもたちの行動が本来定められた範囲から多少外れた場合、たとえば国語のテストの解答を色鉛筆でカラフルに仕上げたというようなことがあっても、答えが正しければほめて評価する、といったような教育方針が採られています。
この施設では障害を持つ子どもが独り立ちできるように力をつけることができるように教育を行っています。苦手分野があってもそれは子どものせいではなく障害があることが原因であるわけですから、障害がある部分に拘泥せずに全人格的な発達を促すことを目的にしているのです。
進学や就職ができずにいたような子どもを受け入れることも多いのですが、この学校で数年間教育を受けることで自分に合った仕事に出会い、無事に卒業していくことも多いようです。
特別支援教育の充実は一般の子どもたちにとっても有用
学習障害やその他の発達障害を持つ人たちは、平成17年に支援の義務づけを定めた発達障害者支援法が成立するまでは法律的なサポートの対象となっておらず「谷間の障害者」などとされることもありました。しかし法律の施行によって国や自治体間でさまざまな施策がなされ始めています。
学校教育の場でも教師に対する研修が行われたり指導する際のマニュアルが整備され始めるなど、発達障害を取り巻く環境は徐々に変化してきています。
日本では、発達障害を持つ子どもは子ども全体のおよそ6%ほどとされています。つまり、40人学級であればおよそ2人か3人の発達障害児が存在することになります。
このため、こうした子どもたちに対する特別支援教育については、担当している教師だけでなくすべての教師に関わる問題となってくると思われ、管理職をしている教師の意識改革や、現場の教員の専門性をより高度なものにすることが必要となるだろうとする専門家もいます。
発達障害を持つ子どもに対する取り組みを行い始めた学校の中には、学校全体の学力がよくなったり不登校のケースが減ったというところもあります。このため、特別支援教育の充実が発達障害ではない子どもにもよい効果をもたらすという指摘もあります。これは、特別支援教育には子ども一人一人についてその実情をつかみ、きめ細かく指導を行っていく特徴があるからだと思われます。
このように日本では発達障害などの子どもは特殊学級などで教育が行われていますが、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなど海外では通常の学級で教育をしているところもあります。
これは、日本では学習障害とされるこうした子どもたちを学習困難者ととらえるという立場の違いがあります。つまり、障害者ではなくて特殊な教育上の必要性を持った普通の子どもとして捉えているということです。その上でそれぞれの子どもたちの実態に即した教育が行われています。
発達障害に対する薬物治療の現状
発達障害の症状にはさまざまな度合いがありますが、障害者本人や周囲の家族が生活に困難を抱えるほどの症状がある場合には投薬治療をするという選択肢もあります。薬剤による治療には危険性はないのでしょうか。
アメリカにおける投薬の実態
言語機能や知能面での遅れはないものの、社会性やコミュニケーション面に問題を抱えるアスペルガー症候群。アスペルガー症候群は自閉症の一つとして分類されている発達障害で、その原因は生まれつき脳に器質面での障害があることとされています。
このため、アメリカではアメリカ食品医薬品局(FDA)が自閉症やアスペルガー症候群に効果のある薬はないとの立場を取っていますが、実際の現場では投薬が行われることは珍しくありません。
こうした障害を抱えた子どもたちに投薬が行われるのは、アスペルガー症候群そのものへの効果を狙ったものではなく、二次的な障害であったり他の発達障害との共存症状を和らげることができるためです。ここで言う二次的な障害というのは不安症状やうつ病といったものです。
例えばアスペルガー症候群を持つ子どもで、抗うつ剤、心臓病の薬(神経の興奮を抑制する効果がある)、向精神薬といったものを処方されるケースがあります。こうした薬を飲むことによって情緒面で落ち着くようになり、暴力行為や集中力の低下といった問題を克服できている場合もあります。
こうした薬を服用することは副作用を伴います。活力が減ってしまったり、体重が増えてしまうといったような副作用が出る場合があります。そうした点については、学校や家でこまめに運動をしたり、体を動かす内容のTVゲームを利用したりすることで乗り切ることができるといいます。
このように、アメリカでは発達障害児に対してさまざまな投薬治療が行われていますし、保護者の間でも投薬治療は肯定的に捉えられる傾向があります。
効果と副作用とをはかりにかける
発達障害を持つ子どもは衝動を抑えきれないという症状があることが多く、このために精神を安定させる薬物やうつ病の薬が投薬されることが多くなっています。こうした薬は脳の内部や神経系に効果を及ぼすということもあり、日本では保護者が拒否反応を示して投薬を拒否することがまま見られるといいます。
注意欠陥・多動性障害(ADHD)に関しては、特徴的な症状である多動や集中力・注意力の低さといったものを抑えるため、メチルフェニデートを成分に含んだリタリンという中枢神経刺激剤が有効だとされています。一方でこの薬による副作用が原因と思われる死亡事例もあり、この薬についてはアメリカにおいても安全性に問題があるのではないかとする専門家がいます。
アメリカにおいては、副作用の危険性があるにも関わらず発達障害の子どもたちにこうした薬剤が投与されています。これは、アメリカの保護者が治療に関して即効性を重視しがちであるという点が理由の一つにあります。
一方で家族など周りの人が症状を理解し、教育面でも配慮を行い、そして感覚器のトレーニングを優先する専門家もいますが、そうであっても障害児本人や家族の生活に支障が出るほどの激しい症状が生じるようならば薬剤を使うことも必要と考えられます。
たとえば発達障害を持つ子どもが自分を傷つけたり自殺したりする危険があるような場合、副作用の危険があるからと手をこまねいていては手遅れになりかねないのです。薬を使うことによって得られる効果と副作用とを視野に入れて考えることが大事になってくると言えるでしょう。
アメリカにおけるメチルフェニデートの処方状況
メチルフェニデートは中枢神経に刺激を与える薬効のある薬剤で、アメリカなどでは注意欠陥・多動性障害の患者のおよそ9割近くに処方され、200万人~300万人が使用しています。しかし一方で、この薬剤がどういった働きをして注意欠陥・多動性障害に診られる症状を除去するのかについては詳しく分かっていません。
注意欠陥・多動性障害については、神経伝達物質の一つであり大脳基底核から分泌されるドーパミンが正しく機能しないために起きると言われています。メチルフェニデートはこのドーパミンの分解を遅らせるとされており、それによって前頭前野の働きが活発になって集中力が出たり、多動性や衝動的な行動が和らげられるのではないかと考えられています。
一方で麻薬のコカインと似たような作用があるという意味での危険性があるほか、副作用があることも指摘されています。またこの薬剤を使うことでその後に薬物濫用に陥る危険性が著しく低下するといった報告もあります。
日本における保険認可の問題
日本において投薬による治療が普及しない理由としては、保護者の拒否感の他に健康保険面の問題があります。例えば、リタリンは難治性のうつ病とナルコレプシー(日中に強い眠気の発作を起こしてしまう脳疾患)にしか健康保険の適用が認められていません。
注意欠陥・多動性障害の薬としてリタリンを申請するためには国内で治験を行うなどさまざまな手続きや費用が必要になるため、製薬会社はそうした申請をしない方針だと言われています。
このことが誤解を招き、リタリンは危険性があるから発達障害の薬として認可されないのだという考え方が一人歩きをしてしまっているのです。また、リタリンが保険の適用外となるため、厚労省はこの薬を幼い子どもに使ってはならないという条件をつけました。こうしたことも誤解を助長しているといいます。
このため注意欠陥多動性障害の子どものうちリタリンが有効だと思われるケースについては、医療現場では保護者にきちんと説明して了承をもらい、注意欠陥・多動性障害に加えてうつ病の診断書を作成したりすることもあるといいます。
アメリカにおいては、リタリンよりも効果が長く持続するコンサータという薬剤が発売されています。このコンサータはリタリンと同じメチルフェニデートを成分として使用している薬剤で、日本においても2007年12月に販売が開始されました。
更新日:2019/11/29|公開日:2015/06/25|タグ:発達障害