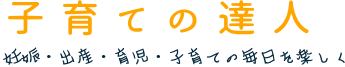世界で最も古く、最も愛される食品「チーズ」の世界にようこそ
「チーズ」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、どんなものですか?アメリカのアニメ漫画でネズミが隠れていた、大きな穴の開いたチーズでしょうか。それとも給食でお馴染みの、三角形で個包装されたあのチーズでしょうか。
世界にはじつに1000種類以上のチーズがあると言われますが、原料となる乳や製造過程は様々で、もちろん匂いや味わいもそれぞれが特徴的です。身近なのによく知らないチーズにはどんなものがあるのかを、歴史も紐解きながら紹介していきたいと思います。
チーズの起源は西アジア、その発見は奇跡的な偶然
チーズを食べたことがない人は、おそらくいないでしょう。様々な料理に食材として使われるだけでなく、フレンチやイタリアンのコースの締めくくりに、ワインと共にいただくこともあります。私達日本人の中には、給食に出された三角形のチーズを思い浮かべる人も多いかもしれません。
最古の加工食品であると言われ、世界中の様々な国で独自に進化してきたチーズですが、その起源は、人類が動物を家畜化してきた歴史と密接に関係しています。なぜなら、チーズを作り食用とするには、原料である「乳」が安定的に供給されなければならないからです。そのためには牛や羊といった哺乳動物を家畜として飼育する必要がありました。
では、人類はいつ頃どの地域で、野生動物を飼いならし「家畜」としたのでしょうか?これには諸説唱えられていますが、帯広畜産大学の平田昌弘准教授の論文『ユーラシア乳文化論』によれば、家畜化の始まりは紀元前8500年頃までさかのぼるそうです。また、食用としての搾乳は紀元前7000年頃、西アジア、いわゆる中東で始まったと見られています。
紀元前2000年頃のアラビアの民話に、こんな話があります。昔、アラビアの商人達は、羊の胃袋で作った水筒に乳を入れ、ラクダに結びつけて砂漠の旅をしていました。喉が渇いたので水筒を開けてみると、中には白い液体と固まりが入っています。試しに固まりを食べてみると、その美味しさに驚いたというチーズ誕生の逸話とも言えるものです。
つまり、羊の胃袋にある酵素が働き、暑い砂漠でラクダに揺られたため、乳が固まりチーズになったという偶然の産物だったわけです。ですが、乳に凝固させる酵素を加え、適温まで加熱し、そこに振動を加えるとホエーと呼ばれる液体と個体に分離できるという原理は、現在でもチーズの製法に生かされている考え方です。
アラビアの商人の話は本当かどうか定かではありません。ですがもし実際にこうやってチーズが生まれたとするならば、砂漠を通って交易を行うようになった紀元前12〜13世紀が、チーズ製造の歴史の出発点であるとも言えるでしょう。
チーズは3つのルートで世界中に広まった
中東地域で生まれたチーズは、徐々に世界中に広まって行きました。そのルートは大きく分けて3つありますが、主に「どうやって乳を固めるか」が異なっており、それぞれ特徴的なチーズとなり、地域に根付いてきました。信州大学名誉教授の大谷元氏によると、次の通りとなっています。
①モンゴルのチーズ
モンゴルを代表する硬質チーズとして知られているのは、「ホロート」です。乳たんぱく質を天日で乾かしたもので、それほど美味しいものではありませんが、低脂肪・高たんぱくで栄養価が高く、長期保存が可能な保存食として重宝されてきました。
一般的なチーズは、乳に酵素を加えて固めますが、モンゴルのチーズ製法では酵素を使用しません。代わりに乳酸菌を使い乳酸発酵させ、その乳を加熱することで乳たんぱくを固めて取り出します。これにより、そのままでは腐りやすい乳をスピーディに加工し、遊牧民の移動生活を支える栄養源となる乾燥チーズを作っています。
②インド・チベットのチーズ
インドで多数派を占める宗教はヒンドゥー教です。そんなインド社会において、牛は神聖な動物として崇められているため、牛肉は決して食べられることはありませんが、牛乳や乳製品は別です。牛を傷つけずに得られる乳はタブーではないため、インドでも積極的に消費されています。
代表的なチーズはカッテージチーズに似た「パニール」や「チェナー(チャーナ)」と呼ばれるフレッシュチーズです。生乳を加熱し、酸を加えて凝固させ、脱水して作るのがチェナーで、チェナーを圧縮したものがパニールです。
ヨーロッパでは子牛の第4胃から取れる酵素を使って乳を固めますが、子牛の殺生を避けるため、インドではこのような製造法を採用しています。
また、チベットにもチーズ作りは伝わっています。有名なものは「チュルビー」と呼ばれる乾燥チーズです。山岳地帯の厳しい環境に適応できるヤクの乳を原料としており、生乳を乳酸菌で発酵させてから加熱して製造されています。
③ギリシャ・イタリアを経由してヨーロッパで根付いたチーズ
西アジアが発祥のチーズ作りは、現在の本場であるとも言えるヨーロッパにも伝わりました。現在存在する数々のチーズの中で最古だと言われるのは、ギリシャのフェタチーズだと言われています。古代ギリシャ・アテネ郊外の羊飼いが作り始めてから現在まで、製法がほぼ変わっていません。
イタリアで最も古くからあるのは、ペコリーノ・ロマーノと呼ばれる羊の乳から作られたハードタイプのチーズです。ローマ帝国の時代から食べられてきたと言われており、保存目的だった当時の製法を受け継ぎ、塩分がかなり強くなっています。
フランス最古のチーズはロックフォールだと言われています。フランス西部の小さな村であるロックフォール村の洞窟の中で熟成させて作られる、個性的な味わいの青カビチーズですが、約2000年の歴史を誇っています。
西アジアから主に3つのルートを辿り、世界中に広まったチーズ作りですが、ヨーロッパに伝わったチーズ作りは、量産を見据えた製法を採用していきます。チーズの製造には、乳を固めるための酵素が欠かせません。西アジアでは羊の胃袋から採れる酵素を利用していましたが、より大量の酵素が手に入る子牛の第4胃を利用するようになりました。
子牛の第4胃を塩漬けにして抽出された「レンネット」という酵素には、たんぱく質を分解する酵素の一種である「キモシン」が多く含まれており、チーズの製造に非常に役立つものです。しかし、レンネットを採取するためには子牛を殺さねばならないため、インドにおけるチーズ作りでは採用されることはありませんでした。
チーズの製法は、どのルートを辿ったかによって、その地域の地形や気候、宗教などの特性に影響を受けて違いがはっきりと現れました。こういった観点でチーズの歴史を振り返ることは、非常に興味深いと言えるでしょう。
なお、ヨーロッパにチーズ作りが伝播した当初は、羊やヤギの乳が主な原料でしたが、その後、イタリアのパルミジャーノ・レッジャーノなど牛乳を原料としたチーズが誕生したと考えられています。これは、穏やかで飼い馴らしやすい羊やヤギを最初の家畜にしたという、野生動物の家畜化の歴史と密接に関わっています。
日本のチーズ製造の歴史は北海道開拓とともに花開く
日本の歴史上、最古のチーズだと言われているのは「酥(そ)」と呼ばれる乳製品で、飛鳥時代の文献に、仏教とともに百済から伝来したと記されています。美容と不老長寿が期待できる超高級食材であり、当時は誰もが口に出来るようなものではなく、貴族など一部の限られた階級の人だけのものだったと考えられます。
他にも中国から、「酪」「醍醐」といった乳製品が輸入され、身分の高い人々に珍重されてきたようです。酥については、国内でも武家政権に変わるまでおよそ600年の間、貴族のための食材として製造されてきましたが、その詳しい製法を文献から窺い知ることはできません。
武家政権の誕生から戦国時代の終焉までの間、日本ではチーズ製造、輸入とも目立った進展はありませんでしたが、江戸時代に入ると大きな動きがありました。オランダから江戸幕府への献上品として、「ゴーダチーズ」が贈られたのです。ゴーダチーズは長期熟成タイプのセミハードチーズで、オランダを代表するチーズとして知られるものです。
明治維新後、日本は急速に西欧化、近代化が進んで行きますが、この時期にキリスト教の布教もさかんになりました。かつてヨーロッパでは、チーズは修道院で作られ、そして民間に伝わって行きましたが、日本でも同様に、開拓時代の北海道を舞台に、修道院がチーズ作りを伝える上で重要な役割を果たしました。
1896(明治29)年に、トラピスト修道院が函館に創立されました。男子修道者たちは石だらけの荒野を耕し、農地を開拓しました。数年後オランダからホルスタイン種の牛5頭が持ち込まれ、乳製品の製造が始まりました。ゴーダ系のチーズを製造し、道内の外国人に販売するようになったのは、創立から8年後のことでした。
北海道内では他にも、女子修道院であるトラピスチヌ修道院でチーズの製造や販売が行われましたが、日本で初めて、白カビタイプのブリックチーズやクリームチーズなどのナチュラルチーズを製造したと言われています。
北海道大学の前身である、札幌農学校の教頭としてウイリアム・スミス・クラークが招かれたのは1876(明治9)年でした。この日本初の近代的な大学は、北海道の酪農業を発展させた町村金弥を輩出しました。町村は4年間の在学中、アメリカ式農場経営を学び、卒業後に本格的にチーズ製造に乗り出します。
卒業後すぐ真駒内牧牛場に赴任した町村は、アメリカ人の牧畜教師エドウィン・ダンのもとバターやチーズの製造法をはじめ、牧畜経営について広く学びました。1926(大正15)年から、町村は門下の宇都宮仙太郎や出納陽一とともに本格的にチーズ製造を始め、1932(昭和7)年には唯一の国産品として販売を行うようになりました。
日本におけるチーズ作りはその後大きく発展していきます。開国、明治維新と激動が続く日本では、北海道の開拓も重要な国策であり、殖産興業の柱の一つでした。町村金弥が師事したエドウィン・ダンは、日本政府が招聘した牧畜指導者であり、ダンの貢献なくして日本のチーズ製造技術の向上はあり得ませんでした。
ダンは、乳牛をアメリカから導入するだけでなく、自ら飼育してみせ、乳製品の加工法も指導しました。また、農機具を利用した、大規模な農場経営を普及させ、北海道の大規模農業の礎を築いたダンですが、町村金弥を始めとする人材を育てたという功績も忘れてはなりません。
チーズの製造に本格的に乗り出したのは、国だけではありませんでした。現在も店頭で見かける「雪印」ブランドの誕生は、1926(昭和元)年に遡ります。北海道製酪販売連合会が「雪印」の商標を取得、その7年後には北海道南部の安平村に遠浅チーズ工場を建設しました。
操業開始当初は、ナチュラルチーズの製造を目指しており、ゴーダチーズやエダムチーズの試作を行っていましたが、物流環境や保存技術が追いついておらず、一旦断念することとなりました。その代わりに取り組んだのが、プロセスチーズの製造でした。
チーズ内部で乳酸菌が自然のままに活動しており、時間が経つにつれ味や香りが変化する「ナチュラルチーズ」に対して、「プロセスチーズ」とは、ナチュラルチーズを原料として、リン酸塩を加えて一旦加熱し、溶かしたものを再び冷やして固めて作るチーズです。長期保存がきき、携帯できるため軍事食として広まった歴史があります。
ちなみに海外では、チーズと言えばナチュラルチーズを指すため、わざわざ「ナチュラル」という言葉をつけて呼ぶことはありません。プロセスチーズが他国と比べても浸透している日本ならではの呼び名だと言えるでしょう。
プロセスチーズの製造に路線転換してからは、年々生産高も拡大を続け、1937(昭和12)年には年間生産高が225トンに達し、東洋一のチーズ工場と謳われるようになりました。これと足並みを揃えるように、プロセスチーズは日本人の食生活に浸透し、乳製品摂取量増加の一端を担うこととなったのです。
第二次大戦後の1963(昭和38)年には、プロセスチーズが学校給食に正式採用され、日本人がチーズに親しむ下地を作りました。同じく給食で供されることが多かったヨーグルトと共に、栄養面でも育ち盛りの児童のカルシウム摂取に大きな役割を果たしたと言えるでしょう。
一方、ナチュラルチーズは1951(昭和26)年に輸入が自由化され、13年後には空輸が開始されました。日本では学校給食の影響もあり、プロセスチーズがより一般的ではありましたが、ナチュラルチーズも徐々に広まり、現在は、日本人の食卓に欠かせない食材となっています。
世界には1000種類のチーズがあり、その分類は至難の業
世界の至る所で、多種多様なチーズが製造され、食べられていますが、全部で何種類あるかご存知でしょうか?答えはなんと、1000種類以上だと言われ、正確な数は専門家でも把握しきれないほどです。その中で世界一の生産高を誇るのは、イギリスが発祥で、牛乳から作られるハードタイプのチーズである「チェダーチーズ」です。
また、国別で最もチーズの種類が多いのは400種類以上もあるとされるフランスです。海洋性、大陸性、山岳性、地中海性の変化に富んだ4つの気候を持つ国だからこそ、「1つの村に1つのチーズがある」と称されるほどのチーズ大国となったのでしょう。
これだけの種類をもつチーズをどのように分類すればよいのでしょうか?チーズの製造プロセスから考えても、様々な視点が生まれ、分類方法は何通りも考えられます。
原料乳の種類を例に考えてみましょう。チーズの製造に使用される乳は主に、牛やヤギ、羊のものが使われています。しかし更に詳細に分類するならば、牛の種類によっても分ける必要が出てきます。飼育数が多いのはホルスタイン種ですが、乳たんぱく質含有量がより多いジャージー種やエアシャー種もチーズ作りには欠かせません。
また、国や地域によっては、牛・ヤギ・羊以外の動物の乳を使ったチーズも作られています。馬やヤクの乳を利用するチベットやモンゴルの他にも、砂漠のある地域ではラクダの乳、スカンジナビア北部のラップランドではトナカイの乳を使ったチーズが作られるなど、簡単には分類しきれない状況となっています。
チーズ王国フランス、そして日本ではどうやって分類しているのか?
世界一チーズの種類が豊富な国、フランスの分類法を見てみたいと思います。日本の分類基準もこのフランス方式を参考に設定されるなど、チーズを理解する上でのスタンダードと考えてよいでしょう。
フランスではチーズ本体の「状態」を大きく5つに分類しています。
①フレッシュ(熟成させていないもの)
②加熱・加圧した(セミ)ハード
③加熱せずに加圧した(セミ)ハード
④青カビ
⑤白カビ、ウォッシュ、自然な表皮をもつソフトタイプ
これに、原料による分類である
⑥シェーブル(ヤギ乳のチーズ)
を加えた6グループによる分類が一般的です。
日本のチーズの分類は、チーズプロフェッショナル協会(CPA)が行いました。フランスを参考にしながらも、次の通り7つのグループに分けています。
①フレッシュ(熟成させていないもの)
②セミハード(加熱せずに加圧したもの)
③ハード(加熱して加圧したもの)
④ソフト(白カビ)
⑤ソフト(青カビ)
⑥ソフト(ウォッシュ)
⑦シェーブル(ヤギ乳のチーズ)
なお、②〜⑦のチーズはすべて熟成チーズです。日本ではまず、熟成タイプなのかフレッシュタイプなのかを分け、その上で熟成チーズを表皮の状態を基本として分類しています。
世界のチーズの代表選手を知ろう
フレッシュチーズと熟成チーズは、美味しいタイミングが違う
フレッシュチーズと熟成チーズの最大の違いはその製法です。フレッシュチーズは、乳に乳酸菌や酵素を加えて固め、水分を取り除いたものです。熟成させないチーズなので、作りたてをすぐ味わうことができ、また、新鮮なものほど美味しくいただけます。一方熟成チーズは、最低でも1ヶ月以上の熟成期間を経てから食べるチーズです。
味わいもまた対照的です。フレッシュチーズは、新鮮な乳の風味が特徴的で、クセのないチーズですので、素材を生かしてそのままいただいたり、お菓子の材料にもよく使われています。
例えばカッテージチーズはカットしたフルーツにたっぷりかけて、クリームチーズはスモークサーモンと合わせてベーグルサンドにと、アメリカの朝食シーンに欠かせない存在です。マスカルポーネチーズは、イタリア料理でなじみ深いティラミスの材料といえば、ピンとくる方が多いかもしれません。エスプレッソやココアパウダーとの相性も抜群です。
イタリアの代表的なフレッシュチーズと言えば、モッツァレラチーズです。そのまま食べると軽い歯ごたえがありますが、加熱すると非常にのびがよく、ピザのトッピングやサラダに使われます。本来は濃厚な水牛の乳を原料として作られていましたが、現在では牛乳のモッツァレラの方が多く流通しています。
フランスのフロマージュ・ブランは、ヨーグルトに似た味わいのチーズです。日本ではフルーツソースと合わせてそのままデザートとしていただいたり、チーズケーキの材料としておなじみですが、本国フランスでは学校給食で出されるなど、国民に浸透しているチーズです。
それでは、熟成チーズにはどのような特徴があるでしょうか?熟成チーズとは、生乳を固める工程で使われた乳酸菌や各種酵素が、その後もチーズの中で生き続け、独特の風味や組織を作り出すタイプのチーズです。
熟成チーズと一口に言っても、その熟成に使われる微生物は様々です。例えば、日本のチーズ分類でいうところの「セミハード」と「ハード」は乳酸菌だけを使って作られており、乳酸菌に白カビを加えると「白カビチーズ」に、青カビを加えると「青カビチーズ」になります。
セミハードチーズとハードチーズの違いは、作り方の違い
「セミハード」と「ハード」チーズの違いは、その製造プロセスにあります。チーズを作るためには、まず乳を酵素で凝固させ、凝乳という物質にします。それを小さなさいの目に切ったものをカードと呼びます。このカードに熱を加えると、ホエー(乳清)が分離し、固まり、つまりチーズが残るという仕組みです。
この際、45℃以上に加熱すると「ハード」、加熱しないと「セミハード」に分類されます。名前のイメージからチーズの固さ、つまり水分含有量による分類だと勘違いされがちですが、フランスの分類法と同じく製法がポイントになっています。
さて、ここでセミハードチーズにはどのような種類があるか、見て行きましょう。セミハードタイプは種類が豊富で、様々な質感や味を食べ比べる楽しみもあります。ゴーダチーズは、オランダを代表するチーズとして日本でもよく知られています。そのままで食べても美味しいですが、サンドイッチに挟んだり、サラダにトッピングしてもよいでしょう。
また、サムソーはデンマークを代表するチーズです。日本には早くから輸入されており、ピザのトッピングなどによく利用されています。他にもフランス・オーヴェルニュ地方のカンタルや北イタリアの「山のチーズ」と呼ばれるフォンティナなどがよく知られています。
それでは、ハードチーズにはどんなものがあるでしょうか。世界一の生産高を誇るチェダーチーズは、このハードチーズに分類されます。熱に溶けやすい性質があり、オムレツに入れたりピザのトッピングにするなど、料理によく利用されます。
スイスの代表的なチーズであるエメンタールチーズは、チーズフォンデュに使われることでも知られています。外国のアニメや漫画によく登場する、穴の開いたチーズはこのエメンタールチーズです。長期間熟成する間に、直径1〜数㎝の丸い穴が開きますが、これは「チーズアイ」と呼ばれ、エメンタールの特徴となっています。
イタリアで製造されるハードチーズで最も知られているのはパルミジャーノ・レッジャーノです。このチーズは本来、40kg以上の大きな円筒形の固まりで、これを切り分けていただきます。何年にも渡って長期熟成を行うのが特徴で、熟成期間の長さにより呼称が変わります。ちなみに、ストラヴェッキオーネと呼ばれるものは48ヶ月熟成を意味します。
白カビと青カビを加えると、熟成による風味が更に増してツウな味わいに
乳酸菌だけを使って長期熟成をするだけでもチーズは味わい深くなりますが、それに加えてカビを表面に植え付けることで、さらに香りや風味が強くなり、とろみのある食感となります。これが、「白カビ」「青カビ」タイプのソフトチーズです。
その始まりは恐らく、カビが生えてしまったチーズを食べてみた誰かが、その美味しさに気付いたことだと言われています。その歴史は古く、2000年前のローマ時代の書物にブルーチーズについての記述があるほどで、長く愛されてきたチーズです。
日本で人気の高い白カビタイプのチーズと言えば、カマンベールチーズでしょう。大変柔らかく、上品でクリーミーな味わいは、食べる人を選びません。日本のメーカーも量産しており、スーパーなどでも気軽に手に入れることができます。中心に少しだけ芯が残った状態が食べ頃で、フルーツに添えたりクラッカーに乗せるなどして楽しんでみましょう。
青カビチーズは俗に「ブルーチーズ」と呼ばれており、人体に無害な青カビを使って熟成させたものです。そのうち、日本で「3大ブルーチーズ」と呼ばれているのは、イタリアのゴルゴンゾーラ、フランスのロックフォール、そしてイギリスのスティルトンですが、実はこの呼称は日本独自のもので、ヨーロッパでは通用しないので注意が必要です。
ゴルゴンゾーラとスティルトンは牛乳が原料ですが、ロックフォールは羊の乳から作られています。また、現在でもフランス・ロックフォール村の洞窟で熟成を行う伝統製法が守られており、この洞窟で熟成させたものだけがロックフォールチーズを名乗ることが許されています。
ブルーチーズは、独特の刺激的な風味と塩気が特徴ですが、ロックフォールは特に、羊の乳の濃厚な味わいと相まった旨味が癖になるチーズです。食べづらいと感じたときは、ドライフルーツやナッツ、またはちみつをプラスしてみましょう。甘味がチーズの強い塩味とマッチして、ぐっといただきやすくなるはずです。
ヤギ乳のチーズは玄人向け、羊乳のチーズはマイルドで初心者向け
シェーブルと呼ばれるヤギ乳のチーズは、酸味がきいた独特の味わいと強い香りが特徴です。そのため初心者向けとは言えませんが、作りたてからかなり熟成したものまで、どの段階でも美味しくいただけるのが良いところです。色々と食べ比べて、好みの熟成具合を見つけるのも楽しいでしょう。
日本で人気が高く、比較的食べやすいのはサントモールです。新鮮な白カビの香りとヤギ乳の風味がうまく溶け合っています。また、ブシェット・ブランシュはクリームチーズのような味わいで、パンやサラダと一緒に朝食の食卓にも似合うチーズだと言えます。
日本のチーズ分類には入っていませんが、羊乳のチーズもたくさん流通しています。「ブルビ」と呼ばれ、脂肪分が高く、こってりとした濃厚な味わいが特徴ですが、シェーブルと比べると癖が少ないため、チーズ初心者や強い風味が苦手な方にも食べやすいチーズです。牛乳のアレルギーがある方にもお勧めです。
羊乳のチーズで有名なのは、イタリアのペコリーノ・ロマーノやスペインのマンチェゴなど、ハードタイプ・セミハードタイプが中心となっています。
ウォッシュタイプは強い匂いが特徴
ウォッシュタイプは、チーズの表皮を塩水や酒で洗いながら熟成させたチーズのことです。表面に植え付けるバチルス・リネンス菌は非常に分解力が強く、強烈な匂いを発し、表面には納豆のような粘りが生まれます。それを数日おきに、塩水やワイン、ビール、ブランデーなど地元の酒で表面を洗い流して熟成させていきます。
また、中世ヨーロッパの修道院で考案されたとも言われており、その洗い方や、回数や使用するアルコールなどは、産地によって様々です。フランス・ノルマンディ地方で作られるリヴァロや、12世紀から修道院で作られていたと言われるポン・レヴェックが知られています。
ナチュラルチーズと呼ぶのは、プロセスチーズが普及した日本だけ
日本のスーパーの店頭には、様々な種類のチーズが並んでいますが、その多くが「プロセスチーズ」と呼ばれるものです。チーズの歴史を振り返った際にも触れましたが、プロセスチーズはその製法から、ナチュラルチーズとは根本的に異なっており、何種類かのナチュラルチーズを原料として作られた加工食品です。
原料となるナチュラルチーズに乳化剤を加えて混ぜ、それを加熱して一旦溶かし、型に流し入れ、冷やし固めて作ります。つまり、乳を固めるのに使用した乳酸菌は殺菌され、酵素の活動も止まった状態となるため、チーズ内部で熟成が進み、味わいが深まるということは起こらなくなります。
日本におけるチーズ普及の歴史から、日本でチーズというとプロセスチーズを思い浮かべる方も多いですが、海外ではチーズとはナチュラルチーズのことを指し、あえて「ナチュラル」と区別して呼ぶこともありません。
プロセスチーズは風味が変わりにくく、長期間の保存が可能なため、戦地における兵士の携帯食として重宝されました。また戦後の日本においても学校給食を通じて、児童のカルシウム源となり、成長を支えた立役者ですが、ぜひナチュラルチーズの味わい深い世界にも足を踏み入れて欲しいと思います。
チーズはまだまだ進化する、新しい製法のチーズたち
チーズは、人々の生活や、その土地の風土によって枝分かれし、進化を続けてきた食品です。従って、これからもライフスタイルや食文化の変化に伴い、チーズも変わり続けていくでしょう。実際、これまでのチーズの分類には収まりきらないチーズが登場しています。
その代表格といえるのは、リコッタチーズです。イタリアで生まれたリコッタチーズは、チーズ特有の臭みが少なく癖がないため、ヨーロッパでは「朝食に最も適したチーズ」と呼ばれ、非常に人気があります。
特徴的なのはその作り方です。一般的なチーズは乳を固めて、乳清(ホエー)と分離させますが、リコッタは本来捨ててしまう副産物のホエーを原料として作ります。ホエーをそのまま、もしくはほぼ同量の乳を加えて再加熱した時に浮いてきた塊を集めたもので、リコッタという名前には「再び煮た」という意味があります。
乳清が原料なので乳脂肪分が少なくさっぱりとした味わいでありながら、乳糖の甘さを感じるリコッタは、そのまま塩とブラックペッパーをかけていただくのがお勧めです。ジャムやはちみつを添えればデザートにもなりますし、パンケーキのタネに混ぜ込んで焼くとコクのある味わいが楽しめます。
ドイツのカンボゾーラというチーズは、1970年代に作られた新作チーズです。表面は白カビが覆っていますが、カットすると断面には青カビが見えます。カマンベールのまろやかさと、ゴルゴンゾーラのピリッとした刺激の両方を同時に味わえる欲張りなチーズですが、2種類のカビ菌のコントロールは高度な技術を要し、安定供給には至っていません。
また、フランスでは、これまで白カビタイプしかなかったシェーブルの青カビタイプを作ったり、ウォッシュタイプが登場するなど、新しい製造技術を取り入れた新作チーズの開発に余念がありません。今後も、健康志向の高まりに合わせ、チーズ開発においても低脂肪や減塩といったキーワードが重要になってくるでしょう。
更新日:2019/11/29|公開日:2017/11/18|タグ:チーズ